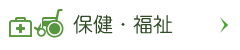令和7年 第一回定例会 区長所信表明
ページ番号:972-898-873
更新日:2025年2月6日
- はじめに
- 令和7年度当初予算案及び令和6年度二月補正予算案
- 子どもたちの笑顔輝くまち
- 高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
- 安心を支える福祉と医療のまち
- 安全・快適、みどりあふれるまち
- いきいきと心豊かに暮らせるまち
- 区民とともに区政を進める
- おわりに
はじめに
所信表明の様子
令和7年第一回練馬区議会定例会の開会にあたり、区政運営に対する所信の一端を申し述べ、区議会並びに区民の皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思います。
友好都市提携30周年を記念して、先週、オーストラリア・イプスウィッチ市のテレサ・ハーディング市長が来訪されました。私が先頭に立って、光が丘の街並みや公園、清掃工場、医療福祉プラザ等の都市施設、大泉町の農園などをご案内しました。都市の利便性と、公園や農地、樹林地など豊かなみどりが両立した、練馬区の魅力を知って頂けたと考えています。また先月、検討に協力してきた「ネリマガーデン」の改修計画がまとめられており、友好の象徴として、永く市民に愛されることを願っています。
歓迎宴で市長からは、「今回の訪問は単なる30周年のお祝いではありません。これからの30年に向けてより強い絆を創るためのものです」とのコメントを頂きました。引き続き、イプスウィッチ市と練馬区の相互理解と友好交流を深めてまいります。
私は財政運営の舵を取るにあたっては、根拠の無い楽観論に陥ることなく、常に一歩先を見据え、いかなる事態にも耐えうる財政基盤を築くことを心掛けてきました。コロナ禍の難局において、ワクチン接種の練馬区モデルや区独自の様々な支援策が実施できたのも、計画的に基金を積み立ててきたからです。
毎年の予算編成では、区民の命と健康を守る事業の推進を最優先とし、区民生活を支える上で必要な施策を、時期を逸することなく確実に実行する一方で、聖域なく既存事業の見直しを徹底してきました。
この10年間を振り返ると、練馬区の福祉医療サービスは飛躍的に充実しました。一般会計の規模は882億円増加しましたが、その約8割、690億円が福祉医療・教育・こども家庭分野です。
保育サービスの充実をはじめ、支援が必要な子どもたちへの対応、地域包括支援センターの体制強化、ひとり親家庭自立応援プロジェクトなどに取り組みました。施設整備面では、病院や介護保険施設、重度障害者グループホームなどに約230億円を充ててきました。区内の病床数は、約1,000床増加し、約2,800床となっています。
こうした施策展開にあわせて、福祉職1.4倍、心理職3.3倍、保健師1.3倍、ケースワーカー1.4倍と、職員体制を増強しました。
基金を610億円から1,160億円へと、550億円増加させるとともに、起債残高の抑制に取り組み、持続可能な財政運営を堅持してきました。財政の弾力性を表す経常収支比率は、86.2%から80.6%へと改善し、適正水準に近づいています。
令和7年度当初予算案及び令和6年度2月補正予算案
令和7年度当初予算は、一般会計予算額が3,517億円、昨年度比286億円の増となっています。学校の改築、道路、公園の整備など、区民生活を支える社会資本を形成する事業には、基金と起債を可能な限り活用しています。
歳入面では、「ふるさと納税制度」による特別区民税の減収が、来年度は58億円に拡大すると見込んでいます。ふるさと納税は、受益と負担という税制本来の趣旨を逸脱し、地方自治の根幹を破壊するものです。しかも、現在は過剰な返礼品競争に堕しています。区は、返礼品競争に与することなく、寄付の充実に向けた取組を進めています。「医療的ケア児・障害児と家族の応援」、「美術館・図書館の全面リニューアル」など、新たに6件の寄付メニューを創設し、目標額を設定して行うクラウドファンディングも活用していきます。
今後とも、ふるさと納税の廃止に向けて、特別区長会全体として、東京都と力を合わせ、粘り強く取り組んでいきます。
また、今年度5度目となる補正予算では、昨年末に成立した国の補正予算を受け、住まいの防犯対策緊急助成事業やキャッシュレス決済ポイント還元事業の実施に要する経費を計上しています。
子どもたちの笑顔輝くまち
次に、子どもたちの笑顔輝くまちについてです。
子育てのかたちを選択できる社会の実現
区独自の幼保一元化施設である「練馬こども園」の創設、「待機児童ゼロ作戦」の展開などにより、これまでに9,200人を超える定員増を実現し、4年連続で待機児童ゼロを達成しました。
保育需要は、0歳児が減少し1・2歳児の増加が見込まれます。このため、定員拡大に向けた私立保育所等への補助制度を新設します。
練馬こども園は、4月から4園が加わり、私立幼稚園38園中30園となります。引き続き、開設準備経費補助や職員への家賃手当 補助を実施し、練馬こども園を拡大します。
障害児保育を充実するため、区立保育園の障害児受入の上限枠を撤廃するとともに、認証保育所への受入に対する補助や、小規模保育施設などへの区独自の人件費補助等により、障害児の受入を更に進めます。
本年秋に、「地域子ども家庭支援センター関」の分室を開設します。これに伴い、子育てのひろばの開室日、乳幼児一時預かりの実施日をそれぞれ週7日に拡充します。
「ねりまママパパてらす」の実施
新たに「ねりまママパパてらす」を実施します。ママやパパが、子育て家庭向けに行う自主講座の運営費等を補助します。児童館や子育てのひろば等で実施する講座の講師を依頼して活躍の場を広げます。地域とのつながりを広げ、子育てを支え合えるよう、交流イベントを開催します。
放課後の居場所づくり
地域・事業者・区の協働により、全ての小学生が安全かつ充実した放課後を過ごすことができるよう環境づくりを進めます。
学童クラブとひろば事業を一体的に行うねりっこクラブは、早期の全校実施を目指して新たに3校で開設し、定員を150人以上拡大します。
特別支援学級のある小学校のねりっこ学童クラブと、児童館等併設学童クラブなどで障害児受入れ枠を35人拡大し、379人とします。
また、保護者の希望により、夏休み等の長期休業中の学童クラブに、児童のお弁当が配達される仕組みを導入します。
支援が必要な子どもたちへの取組
区内の不登校児童生徒数は増加傾向にあり、ニーズに対応した支援を充実します。保健室などに別室登校している児童生徒の学習支援や見守りを行う、校内別室指導支援員を全小中学校に配置するほか、適応指導教室や居場所支援事業の受入人数を拡大します。
社会福祉協議会に「若者ケアラー・コーディネーター」を配置し、18歳以上のケアラーへの支援体制を充実します。関係機関等の連携を密にして、進学や就職などへの対応を強化していきます。
都内初の都児相連携型の社会的養護自立支援事業「ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト」を開始します。
児童養護施設や里親家庭等の手を離れた若者に対し、生活支度金の支給、家賃・光熱水費補助等による生活の支援や、交流や相談の場を提供する居場所支援を行います。
生まれ育った環境によらず、自らの意思で希望する未来を切り拓けるよう、少しでも寄与したいと考えています。
小中学校の改築等の推進
安全で快適な教育環境の整備を進めています。本年1月から中村西小学校、大泉学園中学校の改築設計、豊玉中学校の長寿命化改修設計に着手しています。来年度は、練馬小学校、大泉第二小学校の改築設計、大泉第三小学校、石神井西中学校の長寿命化改修設計に着手します。体育館への空調機設置工事は6校で実施し、全校への整備が完了します。武道場への空調機設置は、当初計画を1年前倒しして着手します。
高齢者が住みなれた地域で暮らせるまち
次に、高齢者が住みなれた地域で暮らせるまちについてです。
地域包括支援センターの移転
団塊ジュニア世代の全てが高齢者となる令和22年を見据え、地域包括ケアシステムを更に推進していきます。
地域包括ケアシステムの中核を担う地域包括支援センターをより身近で利用しやすい窓口とするため、練馬ゆめの木、関町、大泉を4月に区立施設等に移転します。練馬ゆめの木は、名称を「高野台西地域包括支援センター」に変更します。
引き続き、高齢者人口や地域の人口バランスを考慮して、地域包括支援センターの増設・移転、担当地域の見直しに取り組んでいきます。
街かどケアカフェの増設
交流・相談・介護予防の拠点となる街かどケアカフェは、地域包括支援センターの移転等に伴い、常設型を2か所増設します。更に地域サロン型を3か所増設し、全体で48か所とします。
光が丘医療福祉プラザの開設
医療・介護の複合施設「光が丘医療福祉プラザ」を4月に開設します。
介護分野では、介護医療院や看護小規模多機能型居宅介護事業所、医療分野では、緩和ケア病床を備えた157床の病院や在宅医療を担う診療所によって構成します。介護医療院と緩和ケア病床は区内で初の設置となります。また、介護福祉士を養成する「光が丘福祉専門学校」の開設準備が進められています。
近接の練馬光が丘病院などと連携し、入院から在宅生活に至るまで切れ目のない医療・介護サービスを提供します。
介護人材の確保・育成
高齢者人口の増加に伴い、介護人材の確保が急務となっています。人材不足が特に深刻な訪問介護の担い手を確保するため、介護職員初任者研修の受講費用を全額補助に充実するとともに、事業所が受講料を立て替え払いできる仕組みを導入して、本人負担をなくします。
都の訪問介護採用応援事業の対象外である短時間勤務職員を雇用した事業所に対し、区独自に補助を実施します。
介護職員として働く外国人が、地域で孤立せず働き続けられるよう、「光が丘福祉専門学校」と連携して、介護福祉士の試験対策講座や交流会を実施します。
安心を支える福祉と医療のまち
次に、安心を支える福祉と医療のまちについてです。
医療的ケアが必要な障害者への支援の充実
どんなに障害が重くても、住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、障害者のライフステージに応じたサービスを充実します。
三原台二丁目用地を活用した、医療的ケアにも対応した重度障害者の地域生活支援拠点について、先月、整備・運営事業者を選定しました。通いの場の提供、医療型ショートステイ、地域の医療的ケアを支える人材の育成等を実施します。更に特別区の取組としては初となる、医療的ケアが必要な障害者に対する24時間医療・介護が提供される生活の場を整備します。来年度設計に着手し、11年度の開設を目指します。
ひとり親家庭自立応援プロジェクトの充実
平成29年度にひとり親家庭自立応援プロジェクトを発足させ、転宅費用の助成や訪問型学習支援など、23区で最多の取組を実施しています。
貧困による子どもの体験格差が社会問題化するなか、相対的に貧困率が高いひとり親家庭に対しては、多面的できめ細やかな支援が必要です。
新たに、「ひとり親家庭体験格差解消プロジェクト」を実施します。学習の機会を確保するため、学習塾や家庭教師などに利用できるクーポン方式の支援を実施します。親子の体験支援メニューを、コンサートや歌舞伎の鑑賞、読書活動などに拡充します。
あすはステーションの増設
区内2か所目の「あすはステーション」を東大泉敬老館跡施設に開設します。長期間ひきこもり状態にある方等の居場所を提供し、就労準備や職場定着を支援します。
こどもだんらん食堂支援事業の実施
「こどもだんらん食堂支援事業」を新たに実施します。従来の支援金を大幅に拡充し、地域のこども食堂などに対して、開設や運営等に要する経費を補助します。社会福祉協議会では、設立や広報などのアドバイスを行うとともに、こども食堂連絡会を開催してネットワークづくりを支援します。
安全・快適、みどりあふれるまち
次に、安全・快適、みどりあふれるまちについてです。
攻めの防災
昨年は、元日の能登半島地震、被災地を襲った奥能登豪雨、史上初の南海トラフ地震臨時情報が発表された日向灘地震など、災害が相次ぎました。区は攻めの防災を更に強化、加速します。
密集事業を実施している桜台東部地区では、防災道路1号線の用地測量に着手します。貫井・富士見台地区では、四商通り沿道等の用地取得を推進するとともに、無電柱化の設計に着手します。
震災時に救急救命活動や緊急支援物資輸送の大動脈となる道路を閉そくさせないため、重点的に沿道建築物の耐震化に取り組みます。来年度は、一般緊急輸送道路の沿道建築物に対する助成を拡充します。また、迅速な避難行動が難しい障害者や要介護者等が居住する住宅への助成を拡充し、耐震化を促進します。
中高層マンションの在宅避難を促進するため、新たに応急給水栓やマンホールトイレの整備費の助成を行います。「中高層住宅の防災対策ガイドブック」を全面改訂し、全戸配付するとともに、防災フェスタなど様々な機会を活用して、衛生の確保に必要な災害用歯みがきシートなどを配布します。
避難行動要支援者などが健康を維持して避難生活を送れるよう、全避難拠点にエアーベッドを備蓄するとともに、携帯トイレ、アレルギー対応食の備蓄を更に充実します。
住まいの防犯対策
闇バイトによる強盗事件の多発により、不安が高まっています。個人住宅向けの防犯カメラや録画機能付きドアホンなどの購入・設置費用を助成します。防犯意識を高めるため、「防犯・防火ハンドブック」を全面改訂し、全戸配付します。
高齢者セーフティ教室など様々な機会に、振動感知式の防犯ブザーや防犯ガラスフィルムなどを配布し、住まいの防犯対策の必要性を周知していきます。
大江戸線の延伸
練馬区が今後、更に発展を続けていくためには、鉄道や都市計画道路の整備とまちづくりを計画的に進めていく必要があります。
大江戸線の延伸は、副知事をトップとするプロジェクトチームが設置されてから約2年が経過し、今年度末には事業計画素案が取りまとめられる見込みです。今後都は、鉄道事業許可の取得に向けた国との協議を進め、事業計画を確定することとなります。
延伸の早期実現に向けて、区は必要な財源の一部を担うとともに、鉄道施設の整備に協力します。大江戸線延伸推進基金を、来年度更に30億円、その後も計画的に積み増していきます。
新駅予定地周辺では、地域の特性を活かした新たな拠点づくりの検討に取り組みます。大泉学園町8丁目付近に計画している補助233号線沿道では、地区計画原案を作成し、都市計画決定に向けて手続きを進めます。
交通インフラの整備促進とまちづくりの推進
都市計画道路の着実な整備に取り組みます。第4次事業化計画に続く、新たな整備方針の来年度中の策定に向け、都や他の区市町と連携し、道路ネットワークの検証や優先整備路線の検討を進めます。
西武新宿線の連続立体交差事業、側道及び交通広場は、都、鉄道事業者、沿線区市が合同で昨年12月に用地補償説明会を開催しました。引き続き、関係自治体等と連携して用地取得を進めます。
連続立体交差事業にあわせて、上石神井駅、武蔵関駅、上井草駅周辺のまちづくりを推進します。補助135号線の青梅街道から新青梅街道までの区間は、来年度、都市計画事業認可の取得を目指します。
石神井公園駅南口西地区市街地再開発事業では、先月、再開発ビルの新築工事に着手しました。10年度の竣工に向け、区は引き続き再開発組合の取組を支援します。再開発事業区域から富士街道までの補助232号線は、引き続き、地域の皆様に丁寧な説明を行いながら、用地取得を進めます。
先月、「大泉第二中学校の教育環境保全と大泉学園駅南側地区まちづくりの取組方針素案」を地域の皆様にご説明しました。ご意見を頂きながら、年度内の成案化に向けて取り組んでいきます。引き続き、重点地区まちづくり計画を検討する区域の指定など、大泉学園駅南側地区の課題解決に資するまちづくりを着実に進めます。
練馬のみどりを未来へつなぐ
大規模で特色ある公園のみどりを河川や幹線道路のみどりで繋ぎ、ネットワークを形成します。
その拠点である稲荷山公園では、「武蔵野の面影」の再生に向けて、「稲荷山公園の整備に関する専門家委員会」でゾーニング等の検討を進めています。地域の皆様の意見等を踏まえ、段階的な整備のロードマップを策定します。大泉井頭公園では、「水辺空間の創出」をテーマに、8年度の基本計画策定に向けて検討を進めています。来年度は、白子川の源流部となる湧水や、希少な水辺の動植物の自然環境調査を行います。
練馬駅前に立地し区の顔である平成つつじ公園は、来年度から改修工事を実施し、8年度の全面リニューアルオープンを目指します。園内のトイレは、昨年7月に策定した「公園トイレリニューアル方針」のリーディングプロジェクトとして、子ども達のアイデアや、公園利用者の意見などをもとに設計を進め、工事に着手します。今月、トイレのリニューアルを含め、公園全体の改修計画の周知イベントを実施します。
こどもの森を約3,700平方メートルから約8,500平方メートルに拡張します。シンボルとなるツリーハウスや、既存の森を活かした自然体験ゾーンの新設を含め、基本設計に着手します。
いきいきと心豊かに暮らせるまち
次に、いきいきと心豊かに暮らせるまちについてです
産業・都市農業の振興
物価上昇等の影響を受けながらも、売上げ向上や顧客獲得に向け、新製品、新サービスの開発や新市場への参入に取り組む事業者があります。こうした意欲的な事業者を支援するため、今年度から「新規ビジネスチャレンジ補助事業」を開始し、採択枠の2倍の応募がありました。来年度は採択枠を15件から30件に拡大します。
「全国都市農業フェスティバル2025」を11月15日、16日に光が丘で開催します。「買う」「食べる」「体験する」「話す・学ぶ」をテーマに、都市農業の魅力を存分に感じられる様々なイベントなどで構成します。「都市農業サロン」に参加している全国32自治体との連携により、内容を更に充実させるとともに、参加自治体数が前回を上回るよう努めていきます。
美術館・貫井図書館の全面リニューアル
美術館と貫井図書館は、「まちと一体となった」「本物のアートに出会える」「併設の図書館と融合する」という新しい発想のもと、平田晃久氏による個性的な建築物の実施設計を進めています。来年度、コンストラクション・マネジメントを行って建築工事費や工期などを検証し、実施設計完了後、解体工事に着手します。
美術館は大規模な国立、都立があれば用が足りるわけではありません。区立美術館の再整備では、国宝や重要文化財から現代美術、区民の皆様の作品まで、幅広く鑑賞できる環境を整えるとともに、障害の有無にかかわらず、子どもから大人まで、誰もが楽しみ、学び、語る、コミュニティを創出する場とします。区民の皆様とともに地域文化の核となることを目指していきます。
美術館と図書館それぞれの強みを活かして、相乗効果を生み出します。新図書館には、子どもたちが自由に創作活動を楽しめる「ブック・アート・キッズスペース」を設置するなど、身近に本とアートに出会い、感動や発見に繋がる場とします。
中村橋駅周辺のまちなみ整備、アートとまちを繋げる事業の充実などの取組を進めるため、今年度「美術のまち構想」を策定します。
工事による休館中は、ふるさと文化館と連携した展示事業や幅広い年代層を対象とした美術講座などを行います。図書館では、予約資料の貸出等を行う臨時窓口を設置するほか、ブックスタートやおはなし会などの事業を継続します。
11年度の全面リニューアルオープンを目指して、新しい施設での具体的な事業展開について、引き続き検討を重ねていきます。
誰もがスポーツを楽しめる環境の充実
区民の方がスポーツに触れる機会を増やすことを目的に、「(仮称)ねりまスポーツフェスティバル」を区内各所で開催します。フェンシングやユニバーサルスポーツなど、様々なスポーツを体験できるようにします。
障害のあるお子さんが、継続してスポーツを楽しめるよう、区内の総合型地域スポーツクラブと連携して、障害児向けダンス教室を新たに実施します。
総合体育館の改築に向けて、来年度、現在の公共体育館を取り巻く状況、他自治体の最新事例などを調査します。
区民とともに区政を進める
次に、区民とともに区政を進めるについてです。
区民協働の推進
町会・自治会は、区政最大のパートナーです。役員の高齢化や担い手不足等の課題を解決するため、コンサルタントの派遣事業を試行実施します。新たに「デジタル活用促進補助事業」を開始し、加入案内や広報活動などにSNS等を活用できるよう支援していきます。
物価上昇や人手不足の影響を受けて、開催自体が厳しい状況にある地区祭への補助を充実します。
区内2か所目となる地域活動倉庫を平和台地域に整備します。既に既存建物の解体工事を行っており、8年度の開設を目指して整備を進めます。
「ねりま協働ラボ」は今年度から募集を開始し、未来創造チャレンジ1事業、コラボチャレンジ5事業を採択しました。4月から提案の実現に向けて支援を行います。
オンライン化・キャッシュレス化の推進
新たな施設予約システムを導入し、3つに分かれているシステムを統合します。112の施設の検索、予約申込が可能となり、これまでシステム未対応だった図書館と庁舎の会議室など19施設も対象となります。8年1月の予約開始を目指します。
また、10月から、全ての地域集会施設やスポーツ施設などの施設使用料の支払いに、キャッシュレス決済を導入します。
おわりに
私は、生涯をかけて地方自治に従事してきました。行政は目先の人気取りであってはならない。後世の歴史の審判に堪えられる政策を実現しなくてはならない。これを信条として、住民全体の奉仕者、公務員である事を誇りに仕事をしてきました。
これまで全力で取り組んできた、福祉医療と都市インフラという安心の基盤を更に充実しながら、時代の変化に伴う新たな社会の要請に的確に応えるとともに、美術館・図書館の全面リニューアル、総合体育館の改築など、区民生活をより豊かにする施策に力を入れていきたい。大きく動き始めた大江戸線の延伸を1日も早く実現したい。これによって、練馬区はもっともっと発展する、そう確信しています。
区民の皆様にお約束した「改革ねりま第Ⅲ章」を必ず成し遂げる、決意を新たにしています。
区議会の皆様、区民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、本定例会には、これまで述べたものを含め33件の議案を提出しております。宜しくご審議のほど、お願いいたします。
以上をもちまして、私の所信表明を終わります。
お問い合わせ
区長室 秘書課 秘書担当係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202