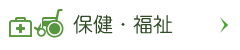令和6年 第二回定例会 区長所信表明
ページ番号:860-424-213
更新日:2024年6月10日
はじめに
所信表明の様子
令和6年第二回練馬区議会定例会の開会にあたり、区政運営に対する所信の一端を申し述べ、区議会並びに区民の皆様のご理解とご協力をお願いしたいと思います。
元日の能登半島地震の発生から5か月余りが経ちました。今なお、多くの方々が日常生活を取り戻せずにいます。一日も早く平穏な暮らしに戻れるよう心から願うとともに、引き続き支援に取り組んでまいります。
区は攻めの防災を加速しています。
密集事業を実施している桜台東部地区では、3月に防災道路一号線の現況測量に着手しました。貫井・富士見台地区では、主要生活道路一号線沿道の用地の一部と、富士見台駅北側の広場用地を取得しています。
4月から両地区に加え防災まちづくり推進地区の旧耐震住宅に対する助成を拡充し、5月には全戸に周知チラシをポスティングしました。また区内全域を対象に、いわゆる2000年新耐震基準を満たさない住宅の助成制度を創設しました。5月末時点で簡易耐震診断の受付件数は、昨年度年間実績の2倍を超えるなど、住宅の安全性への区民の関心は高まっています。
訓練でできないことは、本番でもできません。実戦的な訓練を積み重ねて、いざという時に備えます。3月に、スタンドパイプなどを使って初期消火を体験できる「まちかど防災訓練車」を導入しました。5月末までの2か月間に各地域の訓練で既に27回活用されています。今月、区立施設やコンビニなどへの消火用スタンドパイプの設置を開始します。
平時からの備えも必要です。来月から、携帯トイレ、アレルギー対応食、口腔ケア用品など生活必需品の備蓄を順次増やすとともに、備蓄倉庫を新たに高松と石神井台の2か所で整備します。
1月に着手した避難行動要支援者の個別避難計画は、5月末までに要支援者約32,000人のうち、8,244人が作成しました。引き続き、関係者のご協力を頂きながら作成を進めていきます。
4月には台湾東部で大規模な地震が発生し、防災意識は更に高まっています。私は、区民の生命と財産を守る基礎的自治体の長として、区民の皆様と力を合わせ、攻めの防災の先頭に立って取り組んでいく決意です。
子育て施策
次に、子育て施策についてです。
保育サービスの拡充
区独自の幼保一元化施設「練馬こども園」の創設、「待機児童ゼロ作戦」の展開などにより、10年間で全国トップクラスとなる9,200人以上の保育定員増を実現し、4年連続で保育所待機児童ゼロを達成しました。
区立直営保育園30園で、おむつに続き、「エプロンのサブスク」を開始しました。私立園等でも90園以上でサブスクを導入しています。引き続き、保護者の負担軽減と利便性向上に取り組んでいきます。
全国初となったLINEを活用した保活支援サービスや、電子母子手帳アプリに続き、4月には、「ねりま子育て応援アプリ」の提供を開始しました。これにより、妊娠、出産から子育て期に至るサービスについて、ICTによる情報取得と利用手続が可能になりました。
学童クラブ待機児童対策
4月に区立小学校7校で「ねりっこクラブ」を開設し、8年間で学童クラブの定員は、2,300人以上拡大しました。区独自の待機児童対策「ねりっこプラス」は、34校で実施しています。特別支援学級のある小学校のねりっこ学童クラブでは、障害児受入れ枠を拡大しました。保護者の利便性を向上するため、今月、電子連絡帳アプリを導入し、欠席・早退などをスマホ等で連絡できるようにしました。秋には来年度の入会申請がオンラインで可能になります。
来年度は、全校実施に向け3校でねりっこクラブを開設します。本定例会に、「練馬区ねりっこクラブ条例」及び「練馬区立学童クラブ条例」の改正案を提出しています。
福祉・健康施策
次に、福祉・健康施策についてです。
高齢者、障害者施策
社会全体の高齢化に伴い、ひとり暮らし高齢者や認知症高齢者の増加、障害者の高齢化と重度化、医療的ケアが必要な障害者の増加が見込まれています。誰もが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう取組を進めます。
本年3月、順天堂大学医学部附属練馬病院と認知症施策等の連携に関する協定を締結しました。区が練馬区医師会と連携して実施している「もの忘れ検診」で、更に詳しい検査や診断が必要とされた方の受診を、順天堂練馬病院が積極的に受け入れることとしました。
都市型軽費老人ホームが今月1日に1施設、8月には看護小規模多機能型居宅介護施設が1施設開設します。既にいずれも施設数は、都内最多となっています。
医療的ケアが必要な障害者の通所定員をリーブス練馬高野台で段階的に3名、心身障害者福祉センターで改修が終わる8年度に2名拡大します。
熱中症対策
近年、熱中症による救急搬送者数、死亡者数は高い水準で推移しています。4月には熱中症特別警戒アラートの運用も開始され、熱中症対策は重要な課題となっています。
既に、ねりま情報メールによる熱中症警戒アラートの配信開始など、予防行動への働きかけを強化しています。高齢者や障害者向けに、それぞれの家庭における熱中症の危険を知らせるため、緊急通報システムの入れ替えを進めるとともに、基礎疾患がある方などリスクの高い方には、個別訪問等により呼びかけを行います。
今月1日、88か所の区立施設及び66か所の薬局を、クーリングスポットに指定しました。生活困窮世帯へのエアコン設置補助事業は助成額を増額し、区立小中学校、幼稚園、保育園等子どもが利用する施設には、気化式冷風機や スポットクーラー、熱中症指数計などを導入します。また、学校安全安心ボランティアなどが空調服等を使用できるようにしました。
まちづくり、環境施策
次に、まちづくり、環境施策についてです。
西武新宿線の連続立体交差事業
西武新宿線の連続立体交差事業、都市計画道路補助230号線及び武蔵関駅交通広場は事業認可を取得しました。今後、用地補償説明会を行い、用地取得に取り組みます。今月末には、補助230号線の事業概要・用地補償説明会を開催します。引き続き、都、鉄道事業者、沿線区市と連携して整備を進めます。
鉄道駅のバリアフリー
先月、西武鉄道はバリアフリーの整備計画を公表しました。既に着手している5駅のうち、年度内に石神井公園駅と練馬高野台駅でホームドアが稼働します。また、「整備に向けた検討を進める駅」として大泉学園駅が新たに選定されました。引き続き、西武鉄道と連携して駅の安全性向上に取り組みます。
地域公共交通計画の策定着手
令和8年度の地域公共交通計画の策定に向け、法に基づく協議会を設置しました。南大泉地域で予定しているデマンド交通の実証実験を具体化するため、地域の方々と勉強会を開始します。
公園トイレのリニューアル
昨年度、平成つつじ公園のトイレデザインとアイデアを区内の小中学生から募集しました。この夏には、広く区民から意見を募集します。頂いたアイデアやご意見を活かして設計を進め、平成つつじ公園の全面改修に合わせて、来年度、リニューアルを行います。
区は近く、練馬区のイメージアップを目指す「公園トイレリニューアル方針」をお示しします。平成つつじ公園のトイレはそのリーディングプロジェクトとして位置付ける予定です。
みどりを育むムーブメントの輪
みどりを育むムーブメントの輪を広げていきます。憩いの森等で行われる自然観察会などをスタンプラリーでつなぐ「ねりまの森こどもフェスタ」を開催します。
みどりを育む基金に、「みどりの区民活動応援プロジェクト」を創設し、区民管理団体による樹木剪定や草刈りの取組を支援していきます。
経済、文化施策
次に、経済、文化施策についてです。
スタジオツアー東京開業一周年
アジア初となる「ハリー・ポッター スタジオツアー東京」がオープンして一周年を迎え、本日、アニバーサリーイベントが行われます。
地元商店会からは「国内に加えインバウンドの観光客が増え、売上げも伸びている」といった声が寄せられており、飲食業を中心に賑わいを見せています。また、民間調査会社が2月末に発表した「住みたい街ランキング」では、練馬区が大幅に順位を上げました。「災害に対する安心感」、「地域での顔見知りや知り合いのできやすさ」に加え、「スタジオツアー東京の開業」がその理由として挙げられています。
区では開業一周年に合わせて、16日に練馬城址公園入口スペースで、地元商店会や西武鉄道等と連携したイベントを開催します。個店の魅力をPRするほか、デジタルスタンプラリー、ねりコレ認定店舗による物販などを実施します。
練馬文化センターのリニューアルオープン
練馬文化センターが5月1日にリニューアルオープンしました。音響設備の更新、ホール座席幅の拡張に加え、難聴者を支援するヒアリングループを全席に導入するなどバリアフリー機能を充実しました。リニューアルオープンを記念し、5月26日には人間国宝の野村万作氏、萬斎氏、裕基氏の親子三代による狂言公演を、6月1日には松尾葉子氏の指揮、大谷康子氏・前橋汀子氏のヴァイオリン演奏による「ガラ・コンサート」を開催し、多くの方に楽しんで頂きました。
おわりに
私は大学を出て進路に迷った末に、当時の美濃部都政に惹かれ、日本の社会福祉行政を良くしようと理想を抱いて東京都に入り、希望通り最初の10年間は福祉の現場で働きました。うち6年半が児童福祉でした。若く多感な私は、多摩地区や近県の児童養護施設を訪ねては泊まり込み、子ども達と遊びました。幼い子ども達が若い私に群がって離れない。親の愛情に飢えた子ども達がいじらしくて愛おしくて、この子達のために自分ができることは全てやろうと心に誓いました。私に抱きついてきた、沢山のか細い身体と手足の感触を忘れたことはありません。福祉局では、日本で初めての里親制度の創設、児童相談所の増設と運営の改革、養護施設への家庭的な処遇の導入など、微力ながら力を尽くしました。
この体験から確信しています。全ての子どもには無条件で絶対の愛情が不可欠であり、虐待などトラウマを抱えた子どもには、これに加えて客観的で専門的なケアが必要なのです。この両者を同じ行政主体で担うことはできません。前者は住民に身近な区が相応しく、後者は広域自治体である都が適している。この信念が揺らいだことはありません。
10年前区長に就任した当時、区立児童相談所を設置することが23区の一致した方針となっていました。その理由は「区の方が住民に身近な自治体だから」というだけでした。
私は自分の信念に基づき、練馬区の児相設置方針を変更し、ただ1区、区の子ども家庭支援センターと都の児童相談所との連携強化へと舵を切りました。専門職員の相互派遣に始まり、令和2年には都区共同の「練馬区虐待対応拠点」を設置しました。「虐待対応拠点」は他の3区でも設置され、区児相の設置から都区の連携強化へと方針を転換する区も増えています。
今月1日、都立練馬児童相談所が区の子ども家庭支援センターと同一施設内に開設されました。東京都の方針が明確に示され、東京の児童相談所行政が大きな節目を迎えただけでなく、東京都と特別区の自治の歴史を前に進めるものとなった、そう考えています。
しかし、現状を見ると多数の区立児相と都立児相が併存しています。児童福祉司の育成と交流、施設入所の調整など、広域的な調整機能、専門機能の構築に、都と区が協力して取り組むことが求められています。
家庭の崩壊や虐待などで児相の対象となる子ども達は、最も不幸な存在です。こうした子ども達一人一人の幸せを実現することは、特別区と都の重要な共同の責務です。都立練馬児童相談所と力を合わせ、全力を尽くしてまいります。
区長就任以来、参加と協働を区政運営の根幹に据え、理想の自治体行政を目指して懸命に取り組み、全国自治体を先導する多数の政策「練馬区モデル」を実現してきました。
福祉医療、都市インフラの充実等、これまでの取組を着実に継続・発展させながら、その上に立って、心豊かに生活を楽しめるよう、みどり、文化、スポーツなどの施策に更に力を入れ、グランドデザイン構想で示す練馬区の目指すべき将来像を実現したい、全力で取り組む決意です。
引き続き、区議会の皆様、区民の皆様のご理解、ご協力をお願いいたします。
なお、本定例会には、これまで述べたものを含め20件の議案を提出しております。宜しくご審議のほど、お願いいたします。
以上をもちまして、私の所信表明を終わります。
お問い合わせ
区長室 秘書課 秘書担当係
組織詳細へ
電話:03-3993-1111(代表)
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202