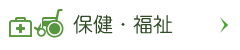令和7年度当初予算案記者発表
ページ番号:798-014-011
更新日:2025年2月14日
日時
令和7年1月23日(木曜) 午後2時00分~午後2時37分
記者会見資料
![]() 令和7年度当初予算案記者発表資料(PDF:14,824KB)
令和7年度当初予算案記者発表資料(PDF:14,824KB)
区長発言
皆さん、お忙しいところ集まりいただきまして、ありがとうございます。
令和7年度の練馬区当初予算案の概要について御説明させていただきます。
私からは、このA3の資料で説明いたします。その他の細部につきましては、御手元に予算資料を配付しております。説明はしませんけれども、それを見ながら、御質問があったら質問していただけたらと思います。
A3の資料を見ていただきますと、大きく3つに分けておりまして、「改革ねりま」をこれまでやってきた、その経緯が1つ目です。
2番目は、令和7年度に向けて、時代変化に伴って新しい事業を始める問題意識が強い事業が3つあります。「ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト」、それから「医療的ケアにも対応した重度障害者の地域生活支援拠点の整備」、さらに「区民との対話から生まれた新しい取組」です。これらは、私が問題意識を持って始めた新しい事業です。
そして、大きな3番目として、区民生活を直接、より豊かにする施策というのを別に挙げております。これは3つありますけれども、後で御説明します。
もう一つ、ここには書いていないのですが、私はこの2年ほど一生懸命やってきたことの一つに、都区制度の改革がありまして、それについては資料を用意しておりませんが、最後にコメントしようと思います。
私は区長就任以来、「改革ねりま」と称して事業を進めてまいりました。様々な練馬区モデルをつくってやってきました。
例えば、単に認可保育所を増やす、そういったことではなくて、今の矛盾した幼稚園と保育所の2園制度、これを変えようと思いまして、練馬こども園を創設してやってきました。それから、ねりっこクラブもそうですね。学校の施設を利用して学童クラブを運営してきました。
さらに、児童相談所は、これは他の22区と反対で、区立は必要ないということで都立方式を取り上げております。
街かどケアカフェ、その他全部そうです。特にコメントをしたいのが2つありまして、1つは、あとで詳しく言いますが、ひとり親家庭自立応援プロジェクトというものです。私の思いもこもっておりますので、また詳しく説明します。
それから、新型コロナワクチン接種です。これは、もう皆さん忘れていますけど、最初の頃は厚生労働省が区市町村の自主的な接種を認めなかったのですよね。ワクチンの冷凍保管と配布が難しいということで。それを首相官邸と相談して、首相官邸から電話がかかってきて、やるというから、じゃあやってくれということで始めたのが、大都市モデルとして新型コロナワクチン接種の練馬区モデルを進めました。ある市が頼まれて、中小市向けのものをやろうとしたのですけど、それはものにならなかったというのが経緯としてありまして、結局、練馬区モデルだけが生き残ったことになりました。
この結果、私が区長になってからの10年間で、決算総額で882億円が増えました。そのうち、福祉医療・教育・こども家庭分野が8割を占めており、この3分野で令和7年度の当初予算案の約7割を占めています。
そういう意味で言うと、福祉医療は特に私が予想した以上に飛躍的に発展したと考えております。
次に、これを支える職員の体制です。特に、福祉事務所を中心に、ケースワーカーと福祉職、それから心理職、保健師を大きく増員いたしました。ケースワーカーは1.4倍増えています。1人当たりの担当世帯数を大きく減らして、人的な意味で大きく充実してきたつもりであります。
これを支えたのは財政です。財政は、私ども区の努力ももちろんあるのですけれども、東京という都市の力が大きく反映しまして、この間、551億円の財政力の増があったと考えています。
一方、起債残高と、公債費負担比率を見ていただくと、こちらは微増ですので、健全な財政を維持したまま区民サービスを充実したと胸を張って言えるかと思っております。
それから、次に個別の話をさせていただきます。
先ほど申し上げました新たな社会の要請に応える施策と申しましたが、これは3つ挙げております。
1番目がねりま羽ばたく若者応援プロジェクトです。
これは、たまたまですけれども、私が行政をやってきた原点の一つであります。私は昭和46年に美濃部都政で社会福祉をやろうと思って、その思いのままに都に入りました。最初に配属されたのが心身障害者福祉センターで、その後は児童部にずっとおりました。障害者福祉と児童福祉が私の原点であります。
この若者応援プロジェクトも児童福祉の一環であります。昔は養護施設に入っている子ども、里親に入っている子どもは、中学校までで終わりだったのです。義務教育だけで終わりだった。それを、私たちが努力して、東京都は高校生まで持っていきました。民間であっても高校生まで進学を認めたのです。
そして、これをさらに進めて、高校卒業後も面倒を見ようというのがこのプロジェクトであります。坂本洋子さんがいらっしゃいますけれども、この方と私は長い長い、もう20数年来のお付き合いで、いろいろな意味でサジェスチョンをもらっています。日本の里親を代表する方ですけども、石原さんが都知事になったときには、一緒に坂本さんのお宅に行ってもらって、懇談したりしました。
我々だってみんな高校を出たら就職するまでは、4年ばかり大学か専門学校に入る人がほとんどなんです。なんで養護施設は18歳になったら追い出すんだ、おかしいだろうということで、里親であっても、それから養護施設であっても、その後の大学進学も認めて、あるいは、その他の専門学校等の頑張りも認め、18歳で措置を解除しないで、自立するまで応援していく、これがそのプロジェクトであります。
これに続きまして、私は、先ほど自分の原点の一つと申しましたけど、そもそも里親制度を日本で初めて本格的につくったのは、自分で言うのもあれですけども、この私であります。私が都に入った昭和46年頃は、養子縁組が里親だというのが日本の伝統的な考え方でした。養子縁組をして、いわば親子関係をつくって、それで面倒を見る。これはおかしいだろうと思いました。
それで、たとえ養子縁組でなくても子どもを育てたいという家庭があってもいいじゃないかということで、東京都で初めてつくったのが養育家庭制度でありました。里親制度は、基本的にこれを中心にして発展しました。
その養育家庭という里親をさらに応援する、養護施設をさらに応援するというのが、ねりま羽ばたく若者応援プロジェクトであります。中身としては、生活の支援として、家具付きアパートを借りる支援をするとか、それから居場所の支援として、お互いにつながり、友人同士、交流する場をつくってあげる。それから啓発事業を行う。こういったこと練馬区がトップに立って初めて始めたわけであります。
次に2番目、医療的ケアにも対応した知的障害者の地域生活支援拠点であります。
私は障害者福祉で長く、色々なことをやってきました。それこそ肢体不自由者や視覚障害者、いろいろな障害者の方々と仕事をしてきました。当時原田政美さんという方がいまして、この方が心身障害者福祉センターの所長でした。この方は、もともとは眼科のお医者さんだったのですけども、昭和天皇の主治医をやっていまして、その方が障害者の行政の道に入ってきて、都の心身障害者福祉センターの所長になっていただいた。大変ありがたかったですけれども、その方に私も頼っていただいて、いろいろな意味で教えていただきました。
例えば、目の視覚障害で、しかも知的障害が重なった子どもたちというのもいるんですよね。両方とも重度である子もいる。そういった子どもたちにどう対応したらいいのか。私は全くの素人でしたから分からなかったのですけど、そこのケアするグループの主任になり、女性のワーカーの人たちと5人で、その子どもたちとお母さんたちの面倒を見ました。
そのときに何をしていいのかと原田さんに教えてもらったのは、どんな子どもであっても持って生まれた素質はあって、その子どもたちの持っている資質、可能性を最大限に花開かせるように支援をして、そして地域社会の生活ができるようにする。それが行政の役割だと、身をもって教えていただきました。
それを今回、こういった形で、こういう子どもたちが一番困っているのは医療的ケアですから、それをできる拠点をつくろうと。
下の四角の表を見ていただきますと、新しくつくるのは(1)本人支援、(2)家族支援、(3)地域の医療的ケアを支える人材の育成等、(4)医療的ケアが必要な障害者の療養介護等となっていますけれども、(1)の本人を支援する、通いの場をつくる。それから、(2)として、家族の介護負担を軽減する、ショートステイの場をつくる。(4)となっているところですが、医療的ケアの一番問題なのは、こういった障害者の皆さんの医療的なケアが難しいところです。例えば痰を切らなくてはいけないから、四六時中面倒をみなくてはいけない。
そういったことをやる人たちがなかなかいないので、それができる場をつくり、短期の入所を認める、あるいは永久の入所を認める、そういった施設を今度初めて練馬区でつくります。
そういう意味での重度障害者の地域生活支援拠点を、こうやって行政が用意して支援をしていくという、初めての試みであります。これは、何とか成功させたいと考えております。これはPRが必要ですけれども、大きく区民の皆さんにも知ってもらおうと思います。
それから、次に、区民との対話から生まれた新しい取組です。
これは2つありますけれども、まず、困難な問題を抱える女性への支援の強化です。
この問題は直接、売春防止法とか、そういったことも関連がありまして、変なところに集められちゃうとか、そういった女性がいますよね。そういった人たちは今までは、昔は売春防止法だけの対応しかなかった。こういった人たちをもっと正面からきちんとケアしようじゃないか。そういう問題を抱えている女性たちが一人で悩んで苦しまないように、ちゃんと居場所をつくる、それから相談も応じる、必要だったら緊急一時保護もできる、そういった場所をつくろうということで、これを頑張っている施設の皆さんと話合いをして、私の決断でこれをやることといたしました。
私は、これに絡んで思うのですけど、母子家庭、ひとり親家庭がありますよね。日本は、本音を言って母子家庭に対する偏見が強い社会だったと思います。いろいろな意味で、例えば女性は身持ちを正しくしなくちゃいけないという、そういった決めつけがあって、それから外れた女性は差別しなくちゃと、そういった意識があって、皆さんは若いから知らないけど、僕らが子どものときは、母子家庭で育った子どもというのは就職も難しいとか、そういった時代があったのです。そういった偏見がずっと続いてきて、こういう人たちの子どもを対象にした児童手当、扶養手当も大した額じゃないのに出し惜しみをするといったことがありました。
私は、これはけしからんとずっと思っていましたので、区長になってすぐ、ひとり親家庭自立応援プロジェクトというのを始めました。それは今もやっておりますけれども、そういった問題への対応の一環として、今度は困難な問題を抱える女性への支援の強化を始めたという次第であります。
それからもう一つ、区民生活をより豊かにしようということで始めた事業が3つあります。
1つは、美術館、貫井図書館の全面リニューアルです。
練馬区の美術館というのは必ずしも十分な施設ではありません。私は、いろいろな区の施設を見に行って、良いなと思う美術館が2、3あったのですけど、そういったところと比べると練馬区は相当落ちるなと思っていました。
ただ、そう言っても国立、都立があるじゃないかという意見もあるかもしれません。それは違うのです。国立、都立は巨大な施設として、それこそ国宝級のものをたくさん持っているという利点があるのですけど、こういう区立の美術館というのは、もっと地域に根ざした国宝、重要文化財から現代美術、区民の皆さんの作品まで幅広く鑑賞できる場でなくちゃいけない。子どもたちも自由に創作活動を楽しめる場にする必要がある。それを図書館と連携した形でつくる、そういった施設をつくろう、そう考えています。
もう一つ、この美術館は、単に美術館だけではなくて、中村橋駅周辺のまちを誰もがアートを感じられるまちとして、その中心となって頑張ってもらう美術館にしたい。そういう、これまで23区ではなかった美術館を目指したいと考えております。
2点目に、総合体育館の改築に向けて、これも美術館と並んで長い懸案ですけれども、老朽化が甚だしい、また、バリアフリーができていませんから、これをできるだけ早く改築に向けてやっていきたい。来年度はそのための調査を始めようと思っています。
それから、もう1点、大江戸線の延伸です。これは直接的に経済効果もあるし、練馬区全体、それから東京都全体にとって大きな事業なのですけれども、これが今、御存じのとおり、都庁内に副知事をトップとするプロジェクトチームをつくって検討して、区も参加して議論をしておりますけど、ちょうど今、正念場に差しかかっておりまして、つくること自体は都の計画で確定しているし、問題ないのですが、問題はいつ着工するか。着工するに当たっては区の負担も必要ですが、区が幾ら負担するか、それを決めなくちゃいけない。それがそろそろ決めるべき時期に来ております。早急に決めて、皆さん方に納得していただきたい、そう考えております。
以上、「改革ねりま」のこれまでの取組と新たな社会の要請に応える施策の説明と、それと区民生活をより豊かにする施策、この3点を御説明申し上げました。
もう1点、ここには書いてありませんが、私は区長になって、特にこの2年間は都区制度を改革したいと思って、区長会でずっと努力を続けてまいりました。東京の特別区制度というのは昔からあるわけじゃなくて、昭和18年につくったものです。
それまでは東京市というのがあり、東京市の市長は選挙で選ばれました。ところが、その選挙をわざわざ廃止して、それを、東京都長官というのを置いて、その長官は国が任命することになりました。なぜかというと戦争遂行のため、戦時体制をつくるためです。それなら戦後になったらそれを変えればよかったのだけど、変えなかった。東京都制度を残してしまった。
しかも、その下に23区をつくりましたが、23区の区長は都が任命する形のものでした。それを改革しなくちゃならないというので、昭和46年に改革したんだけど、そのときは、今度はいきすぎちゃって、23区を全部完全自治体にしてしまった。これは無理なんですよね。
私は児相の問題で何度もお話しましたけど、広域的専門的な行政というのは、本来だったら東京市、23区全体でやる仕事なんです。それを、区に任しちゃいましたから、大変な矛盾が出てきちゃって、児相を持っても結果なかなかうまくいかない。それから、例えば清掃もそうですよね。御存じのように清掃工場がある区というのは本当に限られています。ごみは全地域出ますから、それを調整しながらうまくやらなければいけないし、埋立処分に至っては東京都全体に一つしかないわけですから、これは大問題であって、これは早急に変える必要があると思っているのですけど、ところが、これは区長を公選制にして、区議会も公選にしましたから、なかなか難しい。
放っておいたらいつまで進みませんので、私はこれも改革しようと思って副会長を引き受けて始めた次第でございます。これについては、これからまたもう少し具体的にやっていきたいと思います。取りあえず今はそれだけにしておきます。
私の説明は以上であります。御質問あったらどうぞお受けいたします。
質疑応答
【記者】
東京新聞の浜崎です。本日はありがとうございます。
「ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト」で、都内で初と書いていまして、その次の「重度障害者の地域生活支援拠点」として23区初と書いてあると思うのですけども、改めて、どの部分が都内初、どの部分が23区初かというところを確認でお伺いしたいです。
【区長】
児童福祉法の対象が18歳までですから、18歳を超えたらもう行政的ケアはなくなっちゃうんですね。それを18歳を超えてもケアできるようにしたいというのが、我々の念願です。
それは、本当は制度全体の問題なんだから東京都が考えた方がいいのかもしれないけど、それは待っていられませんから、練馬区が先頭に立って始めます。
こういうことを始めること自体が初めてです。
【記者】
18歳以降も継続して支援するのが都内初で、これは東京都か国か、どこかの自治体に確認されて初めてということでしょうか。
【区長】
私はずっと自分で児童福祉行政をやっていましたから分かっています。福祉局長もやったし、確認するまでもなく初めてです。
【記者】
もう1点、次のページの重度障害者の施設拠点です。これは改めてどういうところが23区初なのでしょうか。
【区長】
23区初というのは、さっきの若者応援プロジェクトも、今までのルールでいけば、むしろ東京都の仕事なんですね。つまり、子どもを収容して養う児童養護施設自体は東京都の仕事だから、その延長に当たるのは、例えば東京都の仕事なんだけど、そういうことを言っていたら何も進まないから、23区である練馬が先頭に立ってやろうというのが、まず、この事業です。
それから、次の重度障害者も、これも御存じのとおり、これまでは区はどちらかといえば、障害が軽い子ども、障害者、大人も含めて、通所の事業を中心にやってきたんですね。
重度重症といって、うんとレベルが重い、両方、身体障害と行動障害、知的障害が混じった人については、東京都がやっています。収容施設をつくって。例えば東村山福祉園とか、そういうところをつくって、そこに入れるというのが従来だったんですね。
それを変えて、できるだけ、重度であっても、重症であっても、地域で暮らせるようにしていきたい。それがもともとの発想なんです。
だから、今までの行政分担でいえば都がやるのが本来なのかもしれないけれども、さっきの子どもと同じで、それを待っていられませんから、練馬区が先頭に立って始めようというのがこの事業です。
実際の需要が多いわけです。特に重度の子どもさんを抱えた親御さんは、自分が亡くなった後にこの子たちは一体どうなるだろうというのが一番の心配ですから、そういう人たちが必要だったら入所して、医療的ケアを受けられるように、そういう施設がほしいと切実に思っているのですね。それに応えていきたいと考えています。
【記者】
そうしますと、ある一定程度の重度の障害者の方の施設というのは、これまで23区内ではなかったということでしょうか。
【区長】
23区がつくっているものはありませんでした。
【記者】
都がつくっている施設等はありますか。
【区長】
例えば、多摩とか、あるいは近県の3県とかに結構ありました。
だから、大規模でいい施設なのですが、そこに入ってしまうと地域生活等何もないわけです。それを変えたいというのが大きな狙いです。
【記者】
朝日新聞の木佐貫と申します。よろしくお願いします。
美術館の件でお伺いしたいと思っておりますけども、この美術館は、今回の解体費用で約5億3千万が計上されていると思うのですけれども、実施設計について、全体の整備費の額というのが出るというお話があったと思うのですが、今どれぐらいの額を見込んでいらっしゃるのか、お伺いしたいと思います。
【区長】
現時点で、この設計を前提にして設計事務所から示されているのは109億円です。
【記者】
ありがとうございます。この取組の中で、7年度は実施設計と並行して、コンストラクションマネジメントを行うとあるのですが、これはつまり、こういう額とか第三者の方に見てもらうと、そういう認識でよろしいでしょうか。
【区長】
こういう手法が今だんだん普及してきて、もちろん第三者の視点も入れながら客観的にどれだけのお金が必要なのか、適切なのか判断するプロセスですね。
【司会】
そちらについては所管課長から説明をお願いいたします。
【美術館再整備担当課長】
美術館再整備担当課長の稲永でございます。
このコンストラクションマネジメントといいますのは、一般的には、そこに注釈で書いてあるプランでございますが、今回は工事工程や積算工事費の妥当性とか、VE・CDの検討支援、またはサウンディング型の市場調査の支援業務等々といったことをお願いしていく予定でございます。
【記者】
そうしたら、これはどういった方にお願いするのですか。例えば専門家とか、どういう方に。
【美術館再整備担当課長】
本日からプロポーザル型の公募を始めるのですが、まず、こういったコンストラクションマネジメントを専門にやっているような事業者さんもおりますので、そういった方に委託していくような形になろうかと思っております。
それについては今後これからという形になっております。
【記者】
ありがとうございます。
109億円ということで、当初は76億円、89億円から109億円となったと思うのですけども、現状、高騰しているような状態だと思うのですが、区長として改めて、今後どのようにこの事業を進めていきたいとお考えですか。
【区長】
美術館に限らないのだけれども、区の建築も都の建築も含めて、ものすごい高騰ですよね。施設によっては、区によってはもうやめちゃうというところも結構出てきています。美術館じゃないけども。
そういう物価の高騰というのは、しっかり見据えていかなくちゃいけないと考えています。そして、当然ながら税金を使ってやるのだから、できるだけ合理的で安い値段にしていきたいと思っております。
ただ、同時に考えなくちゃいけないのは、これはものが美術館ですから、美術館というのは、ただ建物をつくったらいいというわけにはいきませんから、必要なコストと美術館の魅力を保てるだけのコストと、それから、他方で、できるだけ、先ほどお話した合理的で安い値段にしていく。どの辺で折り合いをつけるのか、これは区民の皆さんの御意見も聞きながら、区議会の御意見も聞きながら進めさせていきたいと、そう考えております。
【記者】
コンストラクションマネジメントも行うと思うのですが、そうすると現状、こちらに示されているような建物のデザインであったり、あるいは工期というものが合理的に考えて変更することも考えられますか。
【区長】
それは、答えにくい質問ですね。どんな変更もないかというと、それはいろいろな状況によって変化していきます。柔軟に、しかし、合理的に区民の負担の少ないように対応していきます。
【財政課長】
財政課長の西田でございます。補足をさせていただきます。
先ほど、美術館の御質問の中で、7年度予算額5億3,600万というお話がございました。
これが解体工事費というふうにおっしゃっていたのですけれども、実は内訳がありまして、解体工事については7年度から8年度の2か年にかけて、合わせて6億円を今のところ想定しています。
7年度に計上しているのは、そのうち2億4千万ということになります。
残りは設計であるとか、先ほど申し上げたコンストラクションマネジメント、あるいはまちづくりの方の監修委託、そういったものが入っている。そういった内訳がございます。
【記者】
日経新聞の田崎と申します。大江戸線のところに関して伺いたいと思います。
先ほど少し言及がありましたが、改めて延伸の意義ですとか、区民の期待等を伺えればと思います。
【区長】
大江戸線というのは、区の東北部の公共交通不便地域をなくしていくこともあるのですけども、私どもは、これを通すことは、御存じのとおり、区部で一番の公共交通不便というのは区の東部と西部の縦方向ですよね。これが一番の問題で、これを何とかしなきゃいけないと考えています。
大江戸線を延伸するということは、少なくとも区の西部については、その問題の大きな解決の一助になるし、そしてまた、将来できれば、これは全く私たちの希望だけでありますけれども、埼玉方向にまで伸ばしていけば、東京に限らず、大東京圏のさらなる発展につながるものと思っていますから、それはぜひとも実現したいと思っております。
最近、交通局も大分やる気になってきていますので、一緒にやっていきたいと思います。
【記者】
NHKの後藤です。
「ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト」なんですが、予算をこれだけ積まれていますけど、どの程度のニーズがあると感じられているかということと、改めて、このプロジェクトは都内初ということで、今後期待するところをいただければと思います。
【司会】
それでは、所管課長から数について回答をお願いいたします。
【子ども家庭支援センター所長】
子ども家庭支援センター所長の橋本と申します。
ただいま御質問いただきましたように、対象者の人数等ですけども、区内で児童養護施設を卒業される方が十数名程度といわれています。
その他、私ども子ども家庭支援センターが関わる方々で、18歳以降も支援が必要となる方がいらっしゃいまして、対象としては、20名から40名ぐらいの方が対象になるのかなというふうに考えてございます。
都との連携という部分で、従来であれば、区長が申し上げましたとおり、東京都、主に児童相談所で対応する部分について、私どもとしては、区で地域に根ざしてしっかりと根を張って地域生活をしていただけるように、我々が地域に根ざした支援をする必要があるというふうに考えています。
そういった取組については都内でやっている自治体がございませんので、私どもがしっかりやっていきたいと、そのように考えているところでございます。
【区長】
この問題は、先ほどお話ししたように、児童福祉を長くやっていましたからよく分かっているのですが、日本のこういう子どもの福祉というのは戦災孤児から始まったわけですよね。そういう戦災孤児が何しろたくさんいたから、それをとにかく収容しなくちゃいけないというので、都心ではなくて都外、あるいは多摩にかけて大きな施設を作って、そこに入れていたわけなんですね。それがずっとまだ尾を引いていて、本当に必要な子たちの処遇というのは、そういうことではなくて、もっと家庭的なケアをしてやるとか、それから、できれば里親がいいだろうと私はずっと考えていて、里親制度をつくったりしてやってきました。
その路線で、それをもっとさらに充実して、18歳過ぎた後であっても普通の子ども達と同じように、子どもたちが普通に自立する歳までは、できるだけの支援をやっていきたい、23区の先頭を切って頑張っていきたいと思っています。
【記者】
都政新報社の石井と申します。よろしくお願いします。
新年度予算案について、区長としてどのような考えを持って編成したのか、教えていただけますでしょうか。
【区長】
私が御説明したとおりなんですけれども、これまで進めてきた改革ねりまの路線を、一方では、さらに充実をしていきたい。
それに加えて、来年度新たに始める、私が問題意識を持って始めていきたいのが、ここにある「ねりま羽ばたく若者応援プロジェクト」とか、重度障害者ケアの問題とか、そういった問題。そして、それに加えて、区民生活を直接より豊かにするものとして、お話をした美術館とか体育館とか大江戸線ということを考えています。
その全部が相まって、区民にとってプラスになるようなまちになると思っています。
【司会】
ありがとうございます。
他に御質問のある方は、いらっしゃいますでしょうか。
それでは、これで終わりにさせていただきたいと思いますが、本日は、各担当課長から午後6時半までお問合せに対応させていただきますので、お近くの係員にお声がけいただければ担当課長をお呼びします。
【区長】
最後に一言申し上げます。
私は、長い間、行政をやってきまして、たまたま一番長かったのが東京都で、30数年やってきた。それの一番の出発点となったのが障害者行政と児童行政です。
この2つは、私のライフワークで、今でも、例えば、里親団体と付き合ったり、障害者団体と付き合ったりしてやっていますので、これについていろいろな思いがあって、それをある程度、花開かせて前に進めていきたい。私の念願であります。ぜひとも御理解、御支援をお願いしたい。
【司会】
ありがとうございました。
それでは、これで終了させていただきます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
![]() Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ
お問い合わせ
区長室 広聴広報課 広報戦略係
組織詳細へ
電話:03-5984-2693(直通)
ファクス:03-3993-1194
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202