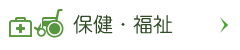帯状疱疹ワクチン任意接種助成事業について
ページ番号:893-125-619
更新日:2025年9月17日
区では、帯状疱疹ワクチンの任意予防接種について、接種費用の一部助成を行っています。
任意予防接種は、予防接種法に基づかない予防接種となっており、ご本人の希望により接種を受けるものです。接種を受けるかどうかは、接種医と相談し、その効果とリスクを理解したうえでご判断ください。
令和7年度の任意接種の助成については、助成内容が令和6年度までとは異なりますので、ご注意ください。
帯状疱疹ワクチンの定期接種については、以下のリンクからご確認ください。
令和7年度の任意予防接種助成事業について
令和7年度の任意接種の助成については以下のとおりです。対象者や助成内容が令和6年度までとは異なりますので、ご注意ください。
対象者
接種日現在、練馬区に住民登録があり、50歳から64歳までの方
(注釈)令和7年度に65歳になる方は対象外です(定期接種の対象者のため)。
(注釈)50歳を迎える方は誕生日前日から接種できます。
対象ワクチンと自己負担額
| 対象ワクチン | 自己負担額 | 接種回数 |
|---|---|---|
| 生ワクチン(乾燥弱毒生水痘ワクチン) | 4,000円 | 1回 |
| 不活化ワクチン(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン) | 11,000円/1回 | 2回 |
- 不活化ワクチンは、標準的にはとして1回目の接種から2か月の間隔をおいて2回目を接種します(2か月を超えた場合は、1回目の接種から6か月後までに2回目を接種します)。
- 1回目に不活化ワクチンを接種した方は2回目に生ワクチンを選択できません。
- 自己負担額は、医療機関の窓口にお支払いください。
- 生活保護受給者および中国残留邦人等給付受給中の方は、自己負担額が免除となります。
予診票
令和7年度中に50歳を迎える方へ、令和7年4月下旬に発送します。
(注釈)令和6年度までの予診票は使えません。令和7年度の予診票がお手元にない場合は、接種を受ける前に予診票の発行手続きを行ってください。
その他
- 助成は、いずれかのワクチンで生涯1度です。
- 入院、施設入所等により区内の予防接種協力医療機関以外で接種された方への助成(償還払い)制度について、詳しくは、こちらをご覧ください。
- 令和8年度以降の任意予防接種の助成事業の継続は未定です。接種を希望される場合は、お早めの接種をご検討ください。
予防接種を受ける場所
練馬区内の予防接種協力医療機関で接種ができます。
帯状疱疹(たいじょうほうしん)について
帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスによって引き起こされる感染症です。ストレスや過労などによりウイルスに対する免疫力が低下すると、神経節に潜伏していたウイルスが再活性化し、神経を伝わり皮膚に到達して、痛みを伴う赤い発疹を生じます。
症状は、皮膚にピリピリとした痛みを感じ、やがてその部分に紅斑と呼ばれる赤い湿疹ができ、その後は水疱ができて破れ皮膚がただれ、かさぶたができます。かさぶたになっても痛みは続き、痛みの度合いは軽いものから夜眠れないほどの強い痛みを感じるものまで様々です。
日本では、70歳代で発症する方が最も多くなっています。また、皮膚症状が治った後も、50歳以上の約2割の方に長い間痛みが残る帯状疱疹後神経痛(PHN)になる可能性があります。
帯状疱疹ワクチンの有効性
帯状疱疹に対する効果 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
|---|---|---|
接種後1年時点 | 6割程度の予防効果 | 9割以上の予防効果 |
接種後5年時点 | 4割程度の予防効果 | |
接種後10年時点 | ― | 7割程度の予防効果 |
合併症の一つである、帯状疱疹後神経痛(PHN)に対するワクチンの効果は、接種後3年時点で、生ワクチンは6割程度、不活化ワクチンは9割以上と報告されています。
副反応について
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。また、頻度は不明ですが、生ワクチンについては、アナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、不活化ワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
接種後に気になる症状を認めた場合は、接種した医療機関へお問い合わせください。
主な副反応の発現割合 | 生ワクチン | 不活化ワクチン |
|---|---|---|
70%以上 | ― | 注射部位の疼痛 |
30%以上 | 注射部位の発赤 | 注射部位の発赤、筋肉痛、疲労 |
10%以上 | 注射部位のそう痒感・熱感・ | 注射部位の腫脹、頭痛、悪寒、発熱、 |
1%以上 | 発疹、倦怠感 | 注射部位のそう痒感、倦怠感、その他の疼痛 |
予防接種による健康被害と救済制度
詳しくは、以下のリンク先をご覧ください。
予診票の発行について
他自治体からの転入、練馬区内での転居、破損、紛失などにより予診票が必要となった方は下記リンク先から発行依頼を行うことが可能です。
よくある質問と回答
他ワクチンとの同時接種は可能ですか?
「生ワクチン」の接種後に異なる「生ワクチン」を接種する場合には、接種間隔を27日間以上あける必要がありますが、それ以外のワクチンの組み合わせ(例:不活化ワクチン接種後に生ワクチンを接種など)では、前の接種からの間隔にかかわらず、次の接種を受けることができます。
練馬区以外で、帯状疱疹ワクチンの接種を受けたいが可能ですか?
定期接種の各ワクチンは、23区等との協定に基づき、練馬区発行の予診票を用いて区外の医療機関で接種できますが、任意接種の帯状疱疹ワクチンは、区独自の助成事業となるため、原則、区内の協力医療機関での接種が助成対象となります。
※入院、施設入所等により区内の予防接種協力医療機関以外で接種された方は、助成(償還払い)制度により費用の助成を行います。詳しくは、こちらをご覧ください。
過去に帯状疱疹にかかったことがあります。この場合でもワクチンの接種を受けることが可能ですか?
帯状疱疹にかかったことがある人も帯状疱疹ワクチンを接種することは可能です。
ただし、帯状疱疹を発症している場合は、症状が軽減するまで、ワクチンの接種を延期すべきとされています。接種が可能かどうかについては、接種医にご確認ください。
過去に全額自費で帯状疱疹ワクチンを接種しましたが、予診票を用いて再接種を受けたいと考えています。接種を受けることは可能ですか?
薬事承認(医薬品や医療機器などの製造販売を厚生労働大臣が承認すること)においては、ワクチン接種完了後から再接種までの期間については示されておりません。接種が可能かどうかについては、接種医にご確認ください。
有効期間切れの予診票を持っています。令和7年度も助成を受けることはできますか。
有効期間の切れた予診票は使用できません。令和7年度の助成対象者で助成を希望する方は、練馬区が今年度に発行した有効期間内の予診票を予防接種協力医療機関に持参する必要があるため、 予診票の再発行手続きを行ってください。
※ご希望の方はお早めの接種をご検討ください。
※帯状疱疹ワクチンの定期接種については、以下をご確認ください。
令和8年3月に50歳になります。予診票の有効期間が短く、3月末までに2回目の接種ができません。令和8年4月以降に接種を受けることは可能ですか?
練馬区の帯状疱疹任意接種助成事業は、東京都の補助事業を活用し、東京都の制度に準じて令和5年度から実施しています。年度単位で実施している助成制度であることから、予診票の有効期間は一律令和7年度末とさせていただいております。
令和8年度の助成事業継続の予定につきましては、決まり次第当ページなどでご案内いたします。
お問い合わせ
健康部 保健予防課 予防接種係
組織詳細へ
電話:03-5984-2484(直通)
ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202