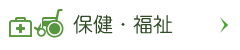野生鳥獣との接し方
ページ番号:503-019-046
更新日:2025年3月18日
野生動物は、厳しい自然環境の中で自らエサを探し、食べて生活しています。人が保護したりエサを与える必要はありません。野生動物が生息できる豊かな自然環境を守るとともに、むやみに近づくことなく静かに見守りましょう。
鳥獣の捕獲・飼育はできません!
鳥獣保護管理法(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律)により許可なく鳥獣を捕獲・殺傷すること、飼うことは禁止されています。違反者には1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます。
野生鳥獣にエサをあげないで!
ハトやタヌキなど野生鳥獣は自然の中で自然の食べ物を食べて生きています。人が野生鳥獣にエサを与えると、エサをもらうことに慣れ、自然の中でエサをとることを忘れてしまい、自力で生きることが難しくなります。さらに、栄養価の高いエサによって病気にかかりやすくなったり、過剰な繁殖が起こります。数が増えすぎた野生動物は生態系を乱す原因となり、鳴き声やフンなどによって私たちの生活環境に被害をもたらします。野生動物は、自然の生態系の中で、自然の食物を食べて生息していくことが本来の姿です。皆さんのご理解とご協力をお願いします。
ケガをした野生動物を見かけたとき
自然環境の中で生きている野生動物は、さまざまなことが原因で弱る場合があります。様子を見て、出血・ケガなどがなければ、そっと見守ってください。出血・ケガがある場合や衰弱している場合は、下記の東京都環境局担当窓口へご相談ください。
野生動物の死体を見かけたとき
野生動物は、飼育されている動物と異なり、餌をとれずに衰弱したり、わずかな環境の変化に耐えられずに死んでしまうことがあります。死体が置かれている場所により対応先が異なりますので、詳しくは以下をご参照ください。
鳥に巣をつくられてしまったとき
・ハトがベランダに巣を作ってしまったとき
巣を作り始めた時点で取り除くか、巣を作らせないことが大切です。巣の中に卵やヒナがいない場合は、巣を撤去していただいて問題ありません。その場合には、使い捨てのビニール手袋やマスクを着用するなど直接触れないように注意してください。
・巣の中に卵やヒナがいる場合
すでに卵やヒナがいる場合には、巣立ちまで見守っていただき、ヒナが巣立ちを終えた後に巣を撤去してください。(ヒナが巣立つまでの期間は長くとも約1か月ほどです。)
巣立ち前に撤去する場合は、捕獲許可をもつ専門業者に撤去を依頼してください(費用は自己負担です。)。
※卵またはヒナを含めた野生鳥獣は許可なく捕獲・殺傷することができません。
・巣をつくられないために
巣の撤去後は、再度巣を作られないよう次のような対処を行ってください。
1.ベランダの風通しをよくし、植木鉢などの物を置かない。
2.ベランダに設置してある洗濯機やエアコンの室外機などの隙間や侵入口をふさぐ。
3.防鳥ネットを張る。
野鳥のヒナが落ちていたとき
巣立ったばかりのヒナ(特に4月から6月)は、うまく飛ぶことができず、地面に落ちてしまうことがあります。親鳥はヒナと鳴き声でコミュニケーションをとっています。人間がいると親鳥はヒナに近づけないので、少し離れて見守りましょう。
※カラスのヒナが落ちていた場合は、親カラスが通行人等を襲うおそれがあります。環境課美化啓発係までご連絡ください。
・カラスの巣をみつけたとき
カラスは繁殖のために3月頃から巣を作り、7月頃までにヒナが飛び立ちます。詳しくは、以下をご参照ください。
カラスにゴミを荒らされるとき
カラスによるごみ集積所でのごみの散乱を防ぐため、網型の防鳥用ネットを無料で貸出しています。詳しくは以下をご参照ください。
アライグマ・ハクビシンによる生活被害を受けたとき
アライグマ・ハクビシンによる生活被害を受けた場合には、区で対応できる場合があります。詳しくは以下をご参照ください。
タヌキを見かけたとき
タヌキは道路の側溝や下水管をねぐらにするなど、都市の環境に順応して生活しています。都市部や市街地周辺で見かけることもありますが、迷い込んでしまったわけではありません。タヌキを見かけた場合にはそっと見守ってあげましょう。
タヌキが家の床下に住み着いている場合は、タヌキがいなくなった後に侵入口をふさぐなど、対処を行ってください。捕獲等をご希望の場合は、捕獲許可をもつ専門業者にご相談ください。
※注釈:タヌキは在来種のため、区は捕獲・保護をしていません。
ヘビを見かけたとき
ヘビは自然の生きものですので、区では駆除や捕獲等は行っていません。ヘビはしばらくするとエサを求めて別の場所に移動しますので、ヘビを見かけても刺激を与えないで、そっとしておきましょう。区内には、アオダイショウ・シマヘビ・ヒバカリ、有毒なヤマカガシなどが生息しています。
<ヤマカガシには注意!>
・毒があり、触れると咬まれる危険がありますので、近づかないようにしましょう。
・全長は60-120センチメートル。
・体色は地域によって異なりますが関東地方では側面に赤色と黒色の斑紋が交互に入ります。
・性質は一般的には大人しいとされていますが、中には攻撃的な個体もいます。
<どうしてもヘビを追い払ったり、駆除したいとき>
ヘビが家の中に入ったなど、どうしても追い払いたい場合は、近づかないで、以下の方法を行うことが有効です。
・ホームセンター等で売っている忌避剤を散布する。
・距離をとり、長い棒で追い払う。
・どうしても駆除したい場合は、専門業者へご相談ください。駆除料金は有料です。
各種お問合せ先
| 内容 | 担当窓口 |
|---|---|
| 野生動物全般の相談 | 東京都環境局自然環境部計画課 鳥獣保護管理担当 電話:03-5388-3505 |
| 駆除の相談 | 公益社団法人東京都ペストコントロール協会 電話:03-3254-0014 |
お問い合わせ
環境部 環境課 美化啓発係
組織詳細へ
電話:03-5984-4709(直通)
ファクス:03-5984-1227
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202