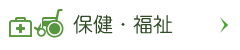こころの健康コラム**専門家からのメッセージ**
ページ番号:191-573-776
更新日:2026年1月6日
『こころの健康コラム』は、さまざまな年代や状況で、多くの方が体験するであろうストレスなどをテーマに、こころの健康にかかわる専門家の方からのメッセージを皆様にお届けいたします。
このコラムをお読みになって、困りごとや不安なことを相談したいと思った方は、こちら(あなたの悩みの相談窓口)をご参照ください。相談内容に応じた相談窓口を紹介しています。
(注釈)執筆者の肩書は、執筆時点のものです。
年代・世代別のテーマ

医療法人社団じうんどう慈雲堂病院院長 田邉 英一 先生
(令和4年度執筆)

医療法人財団厚生協会大泉病院院長 半田 貴士 先生
(令和4年度執筆)
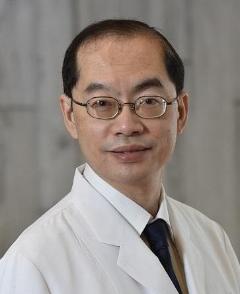
医療法人社団翠会陽和病院院長 牛尾 敬 先生
(令和4年度執筆)

市ヶ谷みぎわ心のクリニック 後藤 恵 先生
(令和5年度執筆)
家族・子育てに関するテーマ
医療法人社団利田会周愛巣鴨クリニック 花田 照久 先生
(令和4年度執筆)
医療法人社団利田会周愛巣鴨クリニック 花田 照久 先生
(令和5年度執筆)

練馬区保健所嘱託医精神科医
とよたまこころの診療所 鷲山 拓男 先生
(令和4年度執筆)
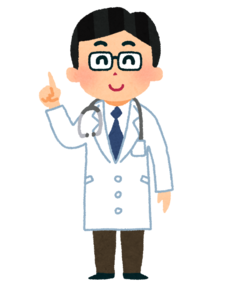
ランディック日本橋クリニック院長 林 寧哲 先生
(令和5年度執筆)

ぱお助産院院長 佐々木 美幸 様
(令和7年度執筆)
こころの不調に関するテーマ
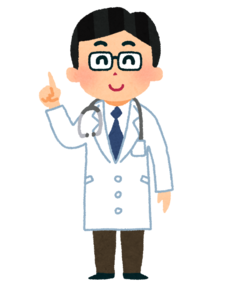
医療法人財団厚生協会大泉病院診療部長 木ざき 英介 先生
(令和5年度執筆)
(注釈)環境依存文字のため、一部仮名書きとしています。

産業医 竹村 雅代 先生
(令和5年度執筆)
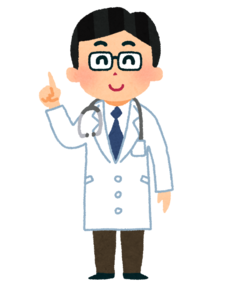
医療法人社団康優会 染谷メンタルクリニック院長 染谷 康宏 先生
(令和5年度執筆)

医療法人社団アパリ アパリクリニック 理事
医療法人社団ヒプノシス 雷門メンタルクリニック 医師
精神科専門医・指導医 梅野 充(うめの みつる) 先生
(令和6年度執筆)
依存症に関するテーマ
医療法人社団ヒプノシス雷門メンタルクリニック院長 伊波 真理雄 先生
(令和4年度執筆)

公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会代表 田中 紀子 様
(令和6年度執筆)
高齢者のこころの健康

医療法人社団じうんどう 慈雲堂病院
院長 田邉 英一 先生
【高齢者のこころの特徴】
超高齢社会となった現代、歳をとってもいきいきと元気に過ごしたいものです。ところがこうした気持ちとは裏腹に、からだの機能は老化が進み、若い頃と違って思うように動きにくくなり、こころの状態にも変化がみられてきます。高齢者のこころの変化の特徴として、記憶を中心とした知的機能の減退、物事の決断が遅くなる、融通が利かなくなり頑固になる等、それまで出来ていたことが出来なくなったり、元来のお人柄がより強く表れるといった性格変化がみられます。また配偶者や親しい友人を亡くしたり、自分自身の仕事からの引退や退職など、社会的にも家庭的にもさまざまな喪失体験を重ねてきて、精神的に不安に駆られやすくなります。自身の健康に関するものも不安の大きな原因となります。さらにこころの変化のなかで最も気をつけなくてはならないものとして、高齢者のうつがあります。
【高齢者のうつの特徴】
高齢者のうつの特徴として、単に気持ちが落ち込み気力が失われるだけでなく、落ち着かずそわそわするような強い不安焦燥感や、からだのあちこちが調子が悪いと訴える心気症状が目立ちます。体調の悪さで診療所や病院を受診しても、特段の異常が見つからない時は、こうしたうつが隠れている可能性があります。また認知症の初期にも、もの忘れにのほかにうつと区別がつきにくい症状がみられることがありますので注意が必要です。
【こころの健康を保つために】
身近なご家族にこうした症状の高齢者がいる場合は、お近くの保健相談所や地域包括支援センターに相談をするか、かかりつけ医や専門診療としての精神科、心療内科を早めに受診しましょう。独居の方の場合には、日頃からできるだけ声をかけてあげましょう。うつや認知症を防ぐために、日頃から人とのかかわりをなるべく保ち、趣味や生きがいを見つけておくことも大切です。練馬区主催の健康講座やさまざまな社会参加の活動がありますので、思い切って参加してみるのもお勧めです。
こころもからだもいきいきと、いつまでも元気さを保ちましょう。
若者のこころの悩み

医療法人財団厚生協会 大泉病院
院長 半田 貴士 先生
【コロナ禍で若者が置かれた特殊な状況】
新型コロナ感染症が流行して以来この数年、社会の閉塞感が強まり、その影響が特に若者のこころに顕著に現れています。入学したのに学校が休校、家でのリモート授業ばかり、クラブ活動もできない、仲間との会食やお喋りも禁止などといった日々が長く続き、友人との交流も持てず、孤立しやすい状況が生まれました。「ひきこもり」がむしろ推奨されるような日々が続いたのです。今でこそコロナによる活動制限は少なくなっていますが、生きているのがつらくなるくらい悩んでいる若者の数が増えています。
もともと思春期、青年期は人生で最も変化の多い不安定な時期です。一人前の大人になるには、学業、進学、友人関係、親からの独立、恋愛、就職、結婚などを無事達成するための多くの発達課題があります。最も成長する時期であると同時に、つまずきやすい時代でもあります。悩んだり自信を失ってひきこもってしまうことは、誰にも起こりうることです。
【若者の悩みの特徴】
若者はまだ人生経験が少ないために、現在の自分の置かれている状況を客観的、俯瞰的にみられず、思い込みが強く極端な考え方に陥りやすい傾向があります。また、「生きる意味とは?」、「自分とは何者か?」など観念的で根源的な思考をするのも若者の考え方の特徴です。
自分が何者であり、何になっていくのかを自己認識することをアイデンティティの確立といいます。現代の複雑な社会では、アイデンティティの確立が30歳くらいまで延びてしまう場合がしばしばあります。この間に自己実現につまずいたり、安定的な人間関係を築けなかったりすると、無力感、自己否定から絶望に至るおそれがあります。
【悩みにどのように対処するか】
1 ひとりで悩まず、相談できる人を見つけよう。
ひとりで悩まないこと、我慢しすぎないことが大切です。信頼できる人を見つけましょう。親や家族、友人、先生など身近に安心して相談できる人がいればいいのですが、逆に近すぎて相談しにくい場合もあります。そんな時は、保健所の保健師さん、学校のカウンセラー、大学や会社の健康管理室などいろいろな相談窓口があります。区のホームページにも相談窓口が載っていますので利用してください。面談ではなく、電話やSNSでの相談もあります。ただSNSでの相談は、相手が誰でどんな人かわからない時には注意が必要です。いろいろな相談を受けても、つらさや苦しみが軽減しない時は、メンタル面の医学的面接、診断、治療を受けることが必要となる場合があります。うつ状態や発達障害のために悩みが生じているケースなどでは、病院の受診も考えて下さい。
2 今だけを見ない。焦らない。「人生は長く、山あり谷あり」
若い時は今が人生のすべてと考えがちですが、人生は長く、どんな厳しい状況も必ず変化します。今の苦しみがずっと続くことはありません。希望を捨てず、変化が良い方向に起きることを信じましょう。早く解決しようと焦ると、逆にさらに追い込まれますので、嵐が過ぎるまでじっと待つことも必要です。あまりにもつらい状況ならば、我慢せずその場所から一時的に逃げ出してひきこもってもかまいません。生き抜くことが最も重要です。若い頃に不登校をして、のちに立派に成功した大人は沢山います。
3 人と比較しない
ある時点だけで自分と人を比較するのはやめましょう。落ち込んでいる時は、他人がよく見えるものです。長い人生ではいろいろな課題や困難があるので、今が順風満帆な人でも後に落ち込む例はたくさんあります。人生に競争はつきもので、劣等感を抱くことは誰にもあることです。自分のペースで自分なりにやっていけばいいのです。「春咲く花もあれば、秋咲く花もある」と思いましょう。
4 居場所と仲間を見つけることが大切
ひとりでひきこもらずに、自宅以外に安心して居ることができる場所が見つかると楽になります。同じような悩みを持っているのは自分一人だけでない、自分だけが特別ではないと分かると安心できます。共感できる仲間が見つかることはうれしいことです。学校に行くことや外で働くことにためらいのある人には、各地域に若者サポートステーション(通称サポステ)という居場所があります。自分の気持ちが落ち着いて、外に歩み出そうと考えられるようになった時には、ぜひ訪ねてみることをお勧めします。
中年期のこころの健康
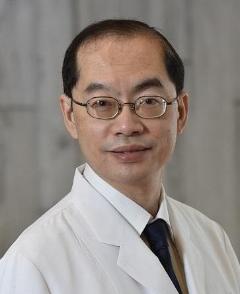
医療法人社団翠会 陽和病院
院長 牛尾 敬 先生
【中年期には第一の人生と第二の人生が交錯します】
およそ45歳から65歳を中年期と呼びます。この時期は様々な経験をつんで自信もつき、安定した成熟の時期と思われるかもしれません。しかし、仕事では責任のある役割を担い、家庭では子どものこと、夫婦のこと、親のことなど、自分以外の人への対応を迫られるようになり、責任の重さや苦悩を感じたり、多忙や過労に悩む人も多くなります。そのような状況のなかで、思い通りにいかないこと、自分の限界、選べなかった人生の悔い、身体の衰えの徴候や疲れ、遠くに見え始める自分の死、などを意識して不安や不満を感じることが出てきます。ユングという心理学者は中年期を「人生の正午」と呼びました。人生の前半と後半が入れかわっていく時期なのです。
【ミッドライフ・クライシス(中年危機)とは】
このような中年期には、個人差はありますが、男性も女性も大小の精神的危機を経験することが少なくありません。そのさなかでは、挫折感や無力感、空しさ、などを感じるかもしれません。でもこの時期は、危機を通りぬけていくことで、第二の人生へ向けた準備をする大事な時期でもあるのです。ユングは「中年期から本当の自己実現が始まる」と言っています。
【自分と向き合うこと】
人はそれぞれ、思春期青年期の試行錯誤を通過して、自分というものや、家庭や社会との関係を作りあげていきます。中年期はそのような第一の人生の頂点にあって、もう一度、自分を見つめ直す時期です。そこから、自分の作り直しが始まります。自分を再定義すると言ってもいいかもしれません。人生後半の課題が始まるのです。
【視点を転換する】
人生の後半を生きるために、多かれ少なかれ、視点の転換が必要になります。それは、心身のケアや生活習慣を見直すことかもしれませんし、原点にかえることや価値観を修正することかもしれません。人によって解決はさまざまです。自分と向き合ってみて、何かを諦めることが解決の場合もあり、チャレンジすることが解決の場合もあります。あるいは、その両方かもしれません。
【うつ病について】
注意しなくてはならないのは、中年期には、うつ病が多いことです。心理的危機や現実的困難がきっかけの場合もありますが、きっかけがはっきりしない場合もあります。不眠、食欲低下、気力低下、身体の不調、憂うつ、不安、状況的には当然と思える悩み、などがうつ病の徴候になり得ます。迷うかもしれませんが、思いきって精神科や心療内科を訪れることが大切です。ご本人や、ご家族でさえ、うつ病と思っていないことがとても多いのです。
【自分ひとりで抱えないことが大事】
状況が行き詰ったと感じたとき、それを打開するためには、人に相談することがとても大事です。もうだめだ、と思っても必ず道は開けます。すぐ解決が得られなくても、人が関わることで変化が始まるのです。視野狭窄も少しずつ開けていきます。最後にひとつだけ、お願いがあります。もし死にたいと思い詰めている方がいらっしゃったら、絶対にひとりで抱え込まずに、必ず相談してください。道は開けます。
若い人たちの心の健康について

市ヶ谷みぎわ心のクリニック
後藤 恵 先生
蛹は蝶の夢を見るでしょうか
蝶になって大空を飛べると知っていたら、蛹になるのも怖くはないかもしれません。でも必ず蝶になれるわけではないし、途中で食べられちゃったりするとしたら、身動きできない蛹になるのって、結構怖いですよね? 子どもから大人になるには、そういう危機を乗り超えなくてはなりません。
【先輩発見の旅に出よう】
若さのただなかに居て、それを楽しむ人たちもいますが、それでも楽しいだけということはありません。なぜなら、若さには未来が見通せないという不安がつきものだからです。家業を継ぐのが宿命であれば、未来は細い道筋ながらも、いくらかは見通せますが、継承に否定的な現代の私たちは、家業を継がない自由とともに、保証のない未来を自分自身で切り開くという責任を負っています。(最近IターンUターンが増えているのは、継承に意味を見出す新しい時代の夜明けかもしれません。)
未来を切り開くなんて難しいことを準備も練習もなしに、いきなり背負わされるのですから、不安と恐怖に震える人がいるのも、当然でしょう。集団を形成して生き延びた私たちホモサピエンスは、ちょっと年上の似た立場の(例えば同性の)もう一人のホモサピエンスを見て、その生き方を見習うという方法で、自分の未来を切り開いています。母親や父親、または叔父や叔母、姉や兄などがお手本になります。しかし、大家族が消滅している現在では、選べる先輩の範囲ははなはだ狭くなっています。ちょうどよい先輩を見つけられたらラッキーです。見つけられない人もたくさんいます。
身近に、マネできそうな生き方をしているお気に入りの先輩が見つからなければ、先輩発見の旅をしましょう。学校の先生や部活の先輩、興味のあるイベントでの出会いなど、お気に入りの先輩探しに出かけるのが正解です。ただし、詐欺集団が跋扈し、SNSでブラックバイトに誘われる、危険がいっぱいの世間ですから、くれぐれも用心してください。あなただけ、今だけお得と言われたら、まずは一歩下がって様子を見る賢さを身に着けましょう。
【比べちゃダメって言われても】
「他人と比べないで」って言われても、比べてしまう年齢があります。苦しい思いをしている若い人たちは、ちょうどそういう年齢です。比べることによって、集団の中で自分の立ち位置を知り、その後の成人としての人生をできるだけ幸せに生きていくために、自分の才能を発見し、同時に限界も発見するために比べっこする時期です。比べているからって、責めたりいじめたりしないでください。むしろ得意分野の発見を喜び、苦手部分は他者に補ってもらう謙虚さを身に着ける良い機会と考えましょう。
比べっこが競争になって、勝利だけが重要だと思い込まされると、大変な苦しみにつながります。勝ち負けを競うことによって、才能が開花したり、もっと磨かれたりすることもありますから、競争がすべて悪ではありません。しかし、勝てば官軍というような、勝つことにだけ意義を見出す態度は、若い人たちにふさわしいとは言えません。
【自分発見プログラムを実行しましょう】
得意分野を見つけたら、比べるよりも、自分の能力や長所を伸ばして、所属集団(人類)に貢献できる力を身につけましょう。家庭や職場、または趣味のサークルのために、その場で役に立つような、自分の能力を探しましょう。今、ありのままの自分で、何ができるか?という、自分発見プログラムを実行します。とびぬけた才能ではなく、比較的少ない努力で、継続的にできることが大切です。誰にでも自分発見プログラムがあり、すべての人に貢献できる能力があります。一番大切なのは、そこに居続ける力です。
集団に所属する第一歩は、そこに参加するところから始まります。仲間の話を聞く力、仲間を観察して適宜援助する力など、目立つことはない普通の能力が役に立ちます。問題を発見して警鐘を鳴らす人、問題解決の方法を提案する人、良さそうな方法を見てついていく人、それぞれに立ち位置があり、価値と重さがあります。先輩や仲間の一言に、自分の存在意義や、得意技発見のヒントが隠されていることもあります。目をみはり、耳をそばだてて、先輩たちの生き方や交渉術を観察しましょう。マネできそうなことは見習いましょう。
自分発見プログラムにコンプリートはありません。少しずつ進めばOKです。
【居場所は探すより造るほうが――】
浜崎あゆみさんの歌が聞こえます。「居場所がなかった」「みつからなかった」
居場所が見つからなくて、苦しい思いをしている人もいるでしょう。居場所を探してさまよって、ここも違う――あそこも違う――。私を受け入れてくれるところなんてない。どこへ行っても誰かが私を批判するし否定する――。そういう人がいないところを探さそうとすると居場所はなかなか見つかりません。
私たちホモサピエンスは、それぞれの所属集団を持ち、そこに居場所を見つけて、居心地よく幸せに生きていくことができる種族です。これは遺伝子に組み込まれた本能ですから、程度の差こそあれ、実は誰にでもある素質であり、能力です。集団は嫌いという人でも、誰かに理解され受け入れられ、愛したり愛されたりして、ほっこり暮らしたいと思う人は少なくありません。
家庭や職場、または趣味のサークルで、その場に貢献する力を発揮すれば、居場所はたちまち見つかります。言い換えれば、自分の能力を生かして貢献すれば、そこにあなたの居場所ができます。一番大切な能力は、そこに居続ける力です。
何もしないで無条件に愛されたいですか?どのような自分でも受け入れてくれる人がほしいですか? それならあなたも誰かを無条件で愛さなくてはなりません。どのようなその人も肯定し受け入れて愛さなくてはなりません。そういう関係もあるでしょう。しかし、普通の人間関係は、普通の人同士の間で再現できる、簡単なものでなくてはなりません。
ほかの人に何かをしてあげる(貢献する)より、誰かに何かをしてもらうほうが得だと思いますか?本当でしょうか?誰かに何かをしてもらいたいのであれば、いつもその誰かが、居なくならないように見張っていなくてはなりません。何かをしてもらいたいなら、そうしてもらえるように、その人のご機嫌を取らなければなりません。面倒ではありませんか?
集団に貢献することがあれば、いつでも自分の自由意思で、集団に出入りできます。貢献できることがあれば、歓迎されますから、どこへ行ってもあなたの居場所はすぐに見つかります。どちらがよさそうですか? 居場所は探すより、造るほうが確実です。所属集団も自由に選べます。誰かのご機嫌を取って、ドキドキしなくても良いとしたら、楽そうに聞こえませんか?
【自分を責めないで】
反省して失敗から学ぶことは大切ですが、失敗にこだわって自分を責めたりいじめたりするのはやめましょう。自分を責めても良い結果は手に入りません。努力した自分を認めて、精一杯ほめて、次に同じような状況になったら、今度はどのような行動をとれば、同じような失敗をしないかと考えましょう。それで充分です。自分を責めると、自己評価が下がり、自信がなくなりますから、前と違う、失敗しない行動をとることが、難しくなります。
依存症の治療では、過去と他人は変えられないと教えます。変えられるのは自分と未来です。素敵なことだと思いませんか?他人を変えるより、自分を変えるほうが、楽ではありませんが、努力すれば実現できます。自分を変える努力をしていれば、その一瞬一瞬が、新しいあなたを創造します。ワクワクしませんか?
【好きなことを探す旅はどこへ?】
今、若い人たちの間には、というか親世代にさえ、「好きなことを見つけてください圧力」が蔓延しています。好きな仕事をしてとか、好きなことさえ見つけてくれればっていう親御さんたち、ちょっと待ってください。そういうあなたは好きな仕事を選びましたか?
「好きなことをして」、といわれると、まじめな人ほど勘違いして、「いやなことをしてはいけない」と翻訳するようです。 何かに挑戦して、いやなことにぶつかると、さっと引っ込んで、「好きなことではなかった」と結論します。「嫌なことをしている自分」は、格好が悪くて恥ずかしいと言う人もいます。
好きなことや仕事は、やってみて、または働いてみて発見するものです。実行しているうちに、この仕事好きかなとか、向いているかもと考えます。 逆に、この仕事より、あちらのほうが良いかも、などと比較して考える力も身につきます。ある程度、現実の世界で、他人の間で働いて(または実行して)みると、「好きなこと」が見つかるのです。
好きな仕事も、大部分はこつこつと積み上げる退屈な手順や作業からなっています。楽しいだけの仕事や、好きなことだらけの仕事はありません。日常的な些細な仕事の中に楽しみや喜びがちりばめられています。楽しいことだらけだったら、楽しみを感じるのに苦労するかもしれません。
【失敗してもやってみる】
まじめな人ほど、失敗してはいけないと思い込んで、身動き取れなくなるものです。でも、失敗は成功の母ですから、失敗を重ねて成功にたどり着くのが普通です。言い換えれば、失敗する覚悟で、何かを実行すると、そこにあなたの道ができます。あなたの人生が、あなたを成功や幸せに連れて行く、あなただけの道が生まれます。踏み出さなければ、振り返っても何もありません。よくわからなくても、「自分の居場所をつくる人」になってみましょう。理解できることだけ実行するほうが、危険が少なくて安全だと感じますか? 赤ちゃんだったあなたが、あんよ して たっち して歩き出すとき、「絶対に歩ける」という確信はなかったでしょう。ただ周囲のお兄さんやお姉さんの真似をしたいという本能にしたがって、やってみたらできちゃっただけです。かっこよく言えば行動療法です。たくさんの自分によく似た先輩がやっていることなら、「やってみたらできる」はずです。
【考えてばかりの人 考えずに行動する人 自分の気持ちを手掛かりにチャレンジしましょう】
考えてばかりで行動できない人は、一歩踏み出すにはどうしたらよいか、相談しましょう。マネできそうな先輩を見つけてください。あまり考えずに、反射的に話したり行動したりする人は、じっくり考える能力を育てましょう。あなたの話を聞いてくれる誰かを見つけて(カウンセラーさんとか)、自分の行動について説明してください。
今までと違う行動をとるには、自分の気持ちが手掛かりになります。自分の気持ちに敏感になりましょう。だからと言って、それを誰かにぶつけて解消することをお勧めしているわけではありません。自分で抱えて味わってください。できない人は、誰かに助けてもらいましょう。
感情は信号機のようなものです。感じると苦しいので、蓋をしている人もいるでしょう。けれど、気持ちの満足がなければ、「好き」や「幸せ」に手が届きません。面倒でも自分の気持ちをキャッチして、味わって、表現して、誰かに伝えてみましょう。共感してくれる人は、あなたの友人や家族になる人です。そう考えれば、自分の気持ちを誰かに伝えるのも、楽しいチャレンジになるでしょう。
そのチャレンジが幸せの扉を開きます。さあ、勇気を出して扉を開けてください。
家族関係とこころの健康 (子の立場から親との関係について)
医療法人社団利田会 周愛巣鴨クリニック
花田 照久 先生
【エリクソンの心理社会的発達から】
乳児は保護者(母親)に受け入れられ、十分に乳を与えられ、眠り、排泄する。
幼児期になると、保護者との信頼関係の中で離乳や排泄のしつけが行われ、遊びや運動の機会が与えられ健全に発達してゆく。保護者の不在や不和、子どもへの虐待、厳格な育児態度(マル・トリートメント)などは子どもの情緒や行動の問題を引き起こすことが多く、成人後のパーソナリティに及ぼす影響も大きい。
学童期となると、学校生活等を通しての社会化と旺盛な知的発達のため両親や家庭の保護的環境から離れ、家族から教師、友人へと子どもの世界は広がってゆく。学校での安定した仲間同士の遊びや学びは、後の社会における対人関係維持の基礎ともなり、子どもにとっては重要な意味をもつ。
乳幼児期に獲得される信頼関係や遊びや運動を通しての体験が十分でなければ、学童期のこころの生活の広がりも十分ではなく、次に迎える思春期(中学・高校生)の身体的・心理的・社会的に激しい変動の時期に、こころの健康に問題が生じることが多くなる。
20世紀(1902年~1994年)アメリカの発達心理学者・精神分析家のエリク・H・エリクソンは、人間の心理社会的発達は上記のように発達していくと語っている。
【子どもの立場から見た保護者(親)との関係】
各年代においての心理社会的発達が達成されない時に生じる問題を私なりに書き加えてみました。
子の立場からの親との関係も上記の発達理論を根底に考えれば以下のように言えると思います。
自らの力で移動できない状態(人間は他の動物より1年早産と言われています)で、十分に乳を与えられ、快く眠り排泄するなどの安心できる体験が乳児の全世界であり、その安心できる全世界を提供してくれる保護者への信頼感(保護者との安心できる関係)を感受することで、子どもにとってはストレスともなる離乳や排泄等のしつけを無理なく受け入れることができ、また遊びや運動も安心してできるようになると考えられます。
成長するに従い活発に遊ぶようになるということは、安心できる世界から興味を感じる未知の世界に向かって独自に行動するわけですが、子どもにとっての興味ある世界は不安な世界でもあり、興味半分、不安半分の世界でありますから、信頼できる保護者の存在や保護者からの見守りが確認できる状態でなければ安心して遊べないわけです。
自らの安全を確認でき、安心して遊ぶことで、子どもは自身の世界を広げていくものだといえます。
私が幼いころ(昭和20年後半)は、テレビはなく、ラジオも身近にない時代でしたので、夜になると祖母が童話の本を読んでくれるのが楽しみでした。数少ない本を毎日読むのですから、内容は暗唱しているくらいです。疲れている祖母の声はモゾモゾした発語で、眠気混じりの独特の寝言の様なリズムでしたが、妹と2人毎晩聞いた事を覚えています。
子どもが何度も本読みをせがむのは、親の注意を求めているためと最近の新聞に書いてあるのを目にし納得しました。
私を背負ったままで近所の人と長話をしている母に、早く止めてほしいと思ったことも、やはり同様な気持ちだったのかなと思います。
自分の周囲の世界に不安・緊張を感じ、保護してくれる存在の確認を子供は常に求めているのだと考えます。
最近電車内でベビーカーに乗った子どもの母へ向けた視線に応えず、スマホに視線を固定している母親をみることがありますが、子どもにとっては寂しく(不安に)感じるのではないかと思います。
保護者が、子どもにとって安心できない存在であれば、安心して遊ぶこともできず安定した日常生活を送ることもできなくなるのではないでしょうか。
学童期になれば、不安・ストレスの多い世界(自分の意志では帰宅できない制限された学校という世界)に長時間身を置くことになるわけですから、学校より帰宅した子どもは、長い航海を終えた船のように疲れており、船にとっての港の様に自宅が子どもにとっての港になることで、翌日元気に登校できるのではないのでしょうか。
子どもにとって家庭は安心できる港であってほしいものです。ゆっくり眠って心身を回復させ、翌日またストレスの多い航海に出かけるわけですから。
小学校の低学年生では、一日学校で体験したことを事細かく報告する子どもがいますが、保護者にむかっての安心の確認行為であり、一日のストレスを癒やす行動だと思います。
前日の疲れが残ったままの航海では海難事故の可能性もあるわけで、事故を避けるための出港延期(子どもたちの「不登校」)も必要になってくるわけです。
不登校の原因としては、学校での問題にスポットが当てられがちですが、家庭内の問題も多いと思います。「家庭内問題」と言っても虐待やドメスティックバイオレンスの様な具体的な問題よりも、日頃の家族内の雰囲気など、客観的に評価できないものが多く、判断は難しいものです。
臨床精神科医として日頃感じることですが、問題化の解消には保護者(両親の)懐の広さが大切な気がしますが、これはまた別の機会があればお話ししたいと思います。
【子供の自死】
ここで、子どもの自死の話しをします。
「コロナ禍での子どもの自殺が急に増えたかのように報じられることが多いが、コロナ禍以前から子どもの自殺は深刻な状態であった。(略) にもかかわらず、令和元年・2年の自殺対策白書で若年層の自殺については、『急増以前の水準に戻っていない』 『自殺死亡率でみると10歳代はほぼ横ばいで推移』などという分析となっている。子どもが危ないという危機感はおろか、増えているという認識すらなかったのである。」 と元防衛医科大学校精神看護学の高橋聡美氏が精神科治療学2021年No8(927P)で語っています。
続けて高橋氏は、「子どもの自殺の原因はいじめだと多くの人が思いがちであるが、残されている遺書をみると、小学生は『家族からのしつけや叱責』、中学生は『学業不振』、高校生は『進路問題』がそれぞれ動機・原因の1位になっている。(略) これは、特別複雑な事情を抱える子どもだけでなく、『親とうまくいかない』 『成績が落ちた』など、普通の暮らしの中でのつまづきで、誰にも相談できず、子どもたちが自死に至っていることを意味する。」と語っています。
それでは「家庭で相談できないか?」ということになるのですが、悩んでいる当人が安心して相談したいと思う人がいなければ、「相談すると批判されてしまう」と日頃思ってしまう家族であれば、『家族からのしつけや叱責』 『学業不振』 『進路問題』の悩みについて話すことはできず、家庭の中で孤立してしまうことになってしまいます。
自死問題を語る時、『居場所がある、ない』という表現をしますが、居場所とは自分の心を許せるような拠り処、前述の「港」のことだと思います。
子どもは成長と共に悩みの内容も変化し、中学・高校生の悩みになると親では対応できないと思われているかもしれませんが、子どもは悩みの答えを求めているのではなく、悩んでいる気持ちを批判なく受け止めて欲しいのだと思います。
「そんなことで悩まないの」 「頑張りなさい」等の励ましは、子どもにとっては安心できる港が閉ざされてしまった気持ちになるのだと思います。
「何もないけど、ここにいれば大きな波はこないから、休んでなさい」と言われるだけで子どもは一息つき、立ち上がってゆくのではないのでしょうか。
【おわりに】
拙論の前半に引用したエリクソンの心理社会的発達理論は有名であり、御存じの方も多いと思います。
各ライフステージにおいて獲得すべき発達課題(乳児期は基本的信頼…といったもの)がありますが、これはあくまでも『理論』であり、「発達課題を完璧に達成させなければ…」といった過剰な意識は持たない方がいいと思います。
子どもの対応については、世の常識とされている一般論・抽象論で判断するのではなく、現実の一つ一つの問題点を保護者独りで考えるのではなく、家族・支援者、そして本人と相談しながら融通をつけて対応していくのが一番大切だと思います。
【続き】家族関係とこころの健康(子の立場から親との関係について)
医療法人社団利田会 周愛巣鴨クリニック
花田 照久 先生
【はじめに】
前回のコラムで、「不登校問題の解消には保護者(両親)の懐の広さが大切な気がします」
とお話ししたため、具体的にお話ししなければと思い頭をかきかきこの文を書いております。
親の懐の広さとは具体的にはどういうことなのか?
子どもの言動にいちいち動揺せず、大らかに優しく時折厳しく見守ることだと考えるのですが、「あなたは出来ますか?」「だから、どうするの?」と問われてしまうと、返事は怪しいものになってしまいます。
前回のコラムで「港」のお話しをしましたが、その「港」でどのように疲れを取れば翌日元気に航海に出られるのか?今回は、わたくし75歳の老人の妄想的ともいえる怪しい独りごとのお話しです。
【遊び育つ子ども】
先日、子どもだけで公園で遊んだり登下校したりすることを禁じるとした埼玉県虐待禁止条例改正案の話しを耳にしました。最初ブラックジョークかと思いました。案の定批判を浴び撤回されましたが、県議会議員が本気で提案した改正案だと考えると、その短絡さに溜息と苦笑いが出てしまいました。
2023年10月19日の朝日新聞朝刊「くらし、HUGSTA」欄に、子どもの遊ぶ権利のための国際協会(IPA)日本支部代表・神戸女子大教授の梶木典子氏の「子どもの遊びを軽視 権利侵害」と題した(談話)記事が掲載され、もやもやした気分が少し楽になりました。
同記事には「埼玉での条例改正案では、まず子供が『遊び育つ』という観点の欠如が問題だと感じました。(略)子どもは、異年齢の子どもの集団である『子ども社会』の中で、遊びを通して思いやりやルールを知り、自己や他者を認識しながら大人になっていきます。(略)そもそも秘密づくりや冒険ごっこは子どもが大好きな遊びですが、大人がいたらその楽しさは激減してしまいます。大人は少しでも危ないとすぐ止めに入ってしまいますが、子どもは遊びの中で「少し危ないかな」という経験をしてリスク管理を学んでいきます。大人の過度な保護は、時に子どもが「やってみたい」と思ったりワクワクしたりする機会を奪うことになるという視点は必要だと思います。(略)遊びは無駄な時間という認識が強すぎないでしょうか。放課後は習い事や塾で時間を過ごすことが多く、友達と予定を合わせて遊ぶことが難しいという声もあります。(略)大人のつくったルールの中で遊ぶのとは違う、自由な遊びが子どもたちには必要です。」と書かれています。
この記事からですと、子供にとっての「遊び」は育つため生き抜くための「遊び育つ」行動であり、大人の「遊び」と異なるものと考えていいのではないでしょうか。子供にとっての「遊び」は、「大人の遊び」ではなく、「仕事」と言ってもいいと思います。
もちろん、子どもが遊ぶ機会を保障するのは行政の役割ということになるのでしょうが、
その前に「遊び」が子どもの成長に不可欠なものであると我々は再認識する必要があると考えます。
【親の懐を広くするもの】
子どもにとっての「遊び」は生きる体験であり、広い社会を感知することであり、必要不可欠なもので、日々の生活のすべてが「遊び」を通して体験され、思いやりやルールを知り、自己や他者を認識しながら大人になっていくのだということでしょう。幼児がちょこちょこ歩きまわるのは意味あることだと思いますが、近頃は発達障害では?…と心配する大人の方もいらっしゃるようです。就学前、幼稚園・保育園時代の子どもの「遊び」は目の届く範囲で安心してほほえましく眺めることが出来るでしょうが、就学後(前回登場のエリクソンの発達理論による「学童期」)は「秘密づくりや冒険ごっこ」「大人のつくったルール」外での「遊び」、それも「少し危ないかな」という経験や、子どもが「やってみたい」と思ったりワクワクしたりする機会を奪わず、少しでも危ないと思ってもすぐ止めに入らず見守ることが大切となると、親は「この子は行く末どうなるのか?悪い癖がつくのではないか、事故・犯罪に巻き込まれるのではないか」いった心配が強くなり、秘密が露見した子どもは父親の心配の裏返しの落雷を受けることになるでしょう。それにもめげずに性懲りもなく繰り返される秘密づくりや冒険ごっこを親はどこまで許容するか、子どもは父親の落雷にひるまず性懲りもなく秘密づくりや冒険ごっこをどこまで繰り返すか、親子関係を崩さず親子の戦いを続けるために不可欠なもの、親の懐を広くするもの、それは何か?
それは6年以上をかけて子どもと作り上げた親子の信頼関係という土台の厚さだと思います。信頼関係は戦いを通して強固される面もあると思いますが戦いにより崩壊することもあるわけで、崩壊防止のために、平和時に休戦交渉に関する条約を締結しておくことが必要かもしれません。そして条約締結のためには平和時の国交・外交が大切となります。
私の周辺でも「ものすごく怒られた」と笑いながら昔を語る人は多くいますし、むやみな落雷のため両親との交流が疎となり距離を縮めることができずこころに傷をもちつつ生きている人も多く知っています。
【親子の信頼関係~おわりに】
親子の安定した信頼関係とは、子どもが親に感じる信頼感と同時に親が子どもに同等の信頼感を持つ双方向の信頼感が成り立つ関係のことであり、外交関係と同じと考えればいいではないでしょうか。 そのために出来ることとしては、家(港)でおしゃべりすること、親子双方が安心してお互いお喋りできる空気をつくること(安定した外交関係)が大切だと思います。お喋りと言ってもなんでもベラベラ喋ればいいというのではなく、嘘をつかなくてもいい気持ち、話したいことをそのまま話していいという気持ちでいられるという雰囲気と言い直した方がいいのかもしれません。
一日働き疲れている両親にとって子どもとのお喋りが負担に感じるかもしれませんが、お喋りすることで親の疲れがとれることもあるのではないでしょうか?
また、「遊び育つ」行動は子どもには楽しい気持ちや満足感を感じるだけではなく、それ以上に緊張感・不安感・苦痛を感じる体験が多いと思います。学校生活以外においてもストレスは多く、またストレスのない遊びだけでは「遊び育つ」ことにはならないともいえるのではないでしょうか?
宮沢賢治の「風の又三郎」、「銀河鉄道の夜」などの作品に登場する子どもたちはストレスだらけの世界で、逞しく遊び育っていると感じます。時代は変りますが、子どもの世界は今も昔も同じと思います。「遊び育つ」ことは子供にとっては生きるための大切な仕事なのです。
家庭とは、ストレスを受けている親子お互いさまの「港」ということになりまして…
当コラムを読み終えてみれば、よくある当たり前のお話でした。
お粗末さまでした。
子育てママのこころの健康のために

練馬区保健所嘱託医精神科医
とよたまこころの診療所
鷲山 拓男 先生
練馬区内の保健相談所で、1990年代前半から保健相談に携わってきました。
保健相談所では、母子手帳交付から妊娠期や出産後の子育て期にわたって、多くの(基本的にすべての)子育てママに出会います。
こころの健康問題をかかえる状態になった妊産婦や子育てママの区民の方々に、保健師とともに直接お会いすることもありますし、援助の方法を保健師と相談することもあります。
私の保健相談所での経験をもとに、子育て中の方もそうでない方も、区民の皆さんにお伝えしたいことをお書きします。
共同の営みとしての私たちの暮らし
私たちは、何万年も前の太古の昔から、群れや集落などの共同体をつくって生活してきました。日頃の暮らしは、共同体のなかで支え合いながら営まれてきました。地域の共同体にたくさんの大人とたくさんの子どもがいて、日々の生活があり、その暮らしのなかで子どもたちは育ちました。「父母と子ども2人」のような核家族が生活の基本単位となったのは、前世紀の途中からのことにすぎません。
哺乳類の多くは母親が子どもを育てます。鳥類の多くは父母のつがいで子どもを育てます。しかし、「社会」をつくって暮らすようになったヒトという名の私たちは、そのどちらでもありません。
子どもたちは地域社会の群れで、多くの大人のかかわる共同繁殖のなかで育ちます。子育ては母親がすべきとか、父母がすべきという発想は、そもそもヒトの暮らしの自然な姿にはありません。
母性神話と3歳児神話
子育てをしているママたちに、私たちは「よい子育て」を、つい教えたくなります。
さまざまな暮らしやさまざまな親子関係があるのに、自分の思う「正しい」子育てを説きたくなります。
しかし、子どもたちは共同の営みの支え合いのなかで、集団のなかで育ちます。
私たち日本人は、戦後の高度経済成長期に核家族化がすすむなかで、母性を過度に神格化してきました。
3歳までは母親が一人で子育てすべきだという「3歳児神話」をいつのまにかつくりあげ、子育て環境の不自然な孤立化を「そうあるべきもの」としました。
養育環境の不十分な子どもを「母親がネグレクトしている」と非難するとき、私たちは育児の責任を母親に押しつけています。
新型コロナウイルス問題下でその傾向がさらに露呈したのは皆さんがみての通りです。
「自粛して下さい」と私たちは育児サービスを突如ママ達からとりあげ、“こういうときくらい子どもは家で母親がみるべき”と圧力をかけました。
では父親が育児に参加すべき?
母性神話が成立した高度成長期から、父親たちは早朝に家を出て、深夜まで帰ってこなくなりました。
1992年に、先進国中最悪の長時間労働を是正すべく「時短促進法」を制定しましたが、その後の経済危機で放棄され、子育て世代の男性労働者の労働時間はむしろ増大しました。
欧州を見習って父親も子育てに参加せよと言ってみたところで、実現する家庭はわずかです。そういう社会をつくってしまったのは私たちです。
私たちのこれから
子どもは社会が育てるという思いをこめた「こども庁」は「こども家庭庁」にかわってしまい、子育てを母親に押しつけるわが国の社会がすぐに変わりそうにはありません。
一方で、子ども食堂のように地域住民が子育てを分かち合う活動が区民の皆さんのなかに広がってきていることを心強く思います。
そのような地域活動を子どもも母親も誰もが、罪悪感やうしろめたさを感じることなく、あたりまえに利用しあえる暮らしが実現することを願っています。
産後うつなどのこころの不調になるママたちは、いまも、これからも、きっと必ずいます。
子育ての負荷がママたちにあまりにも集中しすぎているわが国の現状では、たくさんの不調な人、不調になりかかっている人がいて当然です。
“子育ての仕方をおしえてあげるから頑張りましょう”と指導するのではなく、そのままでいいと保証し、子育ての負担を「群れ」の皆で分かち合い、少しでもママ達に休息を保証して下さい。
「群れ」とは家族のことではありません。
私たち練馬区の皆さんのことです。
NDDの心の健康について ~二次的併存症、診断閾値未満 どうしたらよいか~
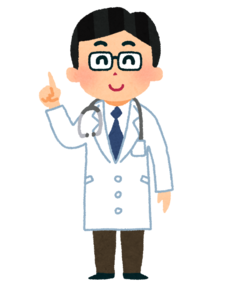
ランディック日本橋クリニック
院長 林 寧哲 先生
練馬区民の皆様こんにちは。
ランディック日本橋クリニック院長の林と申します。
東京日本橋で大人の神経発達症(=発達障害)を専門に携わるようになってから約20年の年月が過ぎ、練馬区の精神保健相談にも長いこと携わっているということもあって、今回コラムの執筆を依頼された次第です。
【二次的併存症 適応障害に焦点をあてて】
昨今、二次的併存症や診断閾値未満(いわゆるグレーゾーン)と言う事が取りざたされており、今回はそれらがどういうものなのかについてお話しさせて頂きます。
まず、二次的併存症とは何でしょうか。
神経発達症などの精神科的疾患に限らず、何らかの疾病に罹患することでその結果として生じてくる病気のことを言います。
体の病気で言いますと二次的合併症と言いますが、精神科の領域でも15年位前までは二次的合併症と二次的併存症という名称が混在していました。
しかし現在は精神科的疾患に関してはあまり二次的合併症という言葉は使われなくなってきているようです。
また二次的併存症という用語は特に神経発達症に伴って生ずるいろいろな問題について使われることが多いようです。
神経発達症の二次的併存症にもいろいろなものがあるのですが、今回は職場のメンタルヘルスにもかかわりの深い適応障害について取り挙げたいと思います。
適応障害にもいろいろあるのですが我々が最も関わることが多い混合性不安抑うつ反応とそれがこじれて長きに亘ってしまった混合性不安抑うつ障害についてお話いたしましょう。
混合性不安抑うつ反応は基本的には一過性で軽度に経過しその罹病期間は一般的には1か月程度で長くとも6か月以内とされています。
それが6か月以上に亘って遷延し程度も比較的強いものを混合性不安抑うつ障害というのだと考えておいてよいかと思います。
その症状は読んで字の如く不安症状と抑うつ症状がともに存在しているのですが、いずれの症状も不安障害とかうつ病とかというほど強くなく、振戦・動悸・口渇・胃蠕動運動の極端な亢進などの自律神経症状が存在していることが特徴です。
このような二次的併存症としての適応障害、混合性不安抑うつ反応・障害は上述した通り神経発達症の専売特許ではなくほかの精神科的疾患(統合失調症や双極性障害、うつ病、様々な不安障害)でも認められるのですが、グレーゾーン即ち診断閾値未満の神経発達症ではその他の疾患より比較的適応性が高いことやおそらくその数が多いことにより問題となることが多いのではないかと思われます。
神経発達症にしてもその他の精神科的疾患にしてもその症状が重篤ですと就労困難或いは就労継続困難ですので、重篤な方々が長きに亘って職場のメンタルヘルスの問題に苛まれることは多くはありません。
重篤ですとそもそも就労できない或いはできたとしても継続できないからです。
就労できてある程度継続が可能な人たちが職場のメンタルヘルスケアに支障をきたし良くなったり悪くなったりを繰り返したりだらだらと軽い不調が遷延して問題となっていることが多いのです。
職場のメンタルヘルスケアで言うところのプレゼンティーイズム(=疾病出勤:出社しているものの業務効率が落ちている状態)やアブセンティーズム(=休業・欠勤)です。
【診断閾値未満の課題について】
いわゆるグレーゾーン=診断閾値未満というのは神経発達症を含むすべての精神科的疾患の診断が現在はICDやDSMの様な操作的診断基準に依ってなされている事に因って生じていると思われます。
操作的診断基準を完全に満たす場合はこれこれと明確に診断されるのですが、操作的診断基準を完全に満たさない場合診断閾値未満と判断します。
一定の基準を満たさないと診断してはいかん、ということになっているのですが、診断閾値未満の方々は基準を満たさなくても生活に支障をきたす症状はいくつか存在していますので生活には支障をきたすわけです。
特に神経発達症の場合、明確に診断されていたとしてもある程度職場に適応できて混合性不安抑うつ反応・障害の様な適応障害を呈さない場合もありますが、そのような場合はその方の特性と職場環境のマッチングがうまくいっている場合が多く、その職場環境に変化(職場の移転・作業内容の変更・異動による人的環境の変化など)が生じたときなどに不適応(=適応障害)が生じ、二次的併存症が発症します。
いわゆるグレーゾーン=診断閾値未満の方々は明確に診断された方々よりもその症状が一定の基準を満たすほど多くないという点に於いて会社や社会への適応性が比較的高いことが多いのですが、そうはいっても仕事や生活に支障をきたす症状がないわけではないので、明確に診断された方々と同様に不適応を呈することがあるのです。
職場のメンタルヘルスに於いては明確に診断された方々はもちろんですが診断閾値未満の方々も問題を生ずることはあり、おそらく明確に診断された方々よりも診断閾値未満の方々の方が数は多いと考えられますので診断閾値未満の神経発達症が職場のメンタルヘルスに重要な意味を持っているものと考えられます。
【二次的併存症が発症しないために】
この様に職場のメンタルヘルスに大きな影響を及ぼす二次的併存症(適応障害=混合性不安抑うつ反応・障害)ですが、
そうなってしまわないためにはどうしたらよいのでしょうか。
そうなってしまったらどうしたらよいのでしょうか。
当院は成人期神経発達症専門で診療をしている関係上、神経発達症あるいはその診断閾値未満の方々を対象に治療を行っておりますが、適応障害=二次的併存症が問題になっている患者さんに対して普段お話ししている内容についてお話しさせて頂きます。
そうなってしまわないためには、二次的併存症が発症しないためにはと言う事でお話ししていることは、
ライフスタイルを適切に維持するということです。
具体的に言いますと
平日も休日も朝起きる時間と夜寝る時間は一定を維持することです。
運動は脳の機能を維持することに寄与しますので日常的に運動することがルーティンとなるように生活を組み立てるようにとも指導します。
仕事との兼ね合いでなかなか難しいことが多いのですが、できれば早寝早起きが望ましいということも伝えます。
また、仕事以外の生活自体をおろそかにしないことも大切です。これをおろそかにしていることで調子を崩している方々がたくさんいます。
身支度や家事などは自分なりにパターンを作って自動的にできるだけ労が少ないように尚且つ抜けがないように順番を決めて、日常的にやらなければならないことの種類によっては毎日ではなくて週に1回とか2回とかタスクを分割する必要性についても指導することがあります。
仕事の仕方に関しては、調整可能な範囲でということになりますが、
自分自身の許容量を把握してそれを超えないように70-80%を心掛け
飛ばしすぎて電池切れにならないように気を付けるようにと指導しています。
これもなかなか難しいことではありますが、自分の適性に合った仕事を選ぶと言う事も重要な要素でしょう。
【二次的併存症が発症してしまったら】
そうなってしまったら、二次的併存症が発症してしまったらどうするか。
たいていの場合新規の混合性不安抑うつ反応であったり混合性不安抑うつ障害の増悪であったりと言う事が多いのですが、
仕事に於いても生活に於いても色々とうまくいかないことを思い悩んで脳がくたびれ切ってしまった状態と考えていただいてよいでしょう。
くたびれて動けないときは休むのです。
休んで英気を養って生活を整えて行くために一定期間仕事を休んで自宅療養することを勧めます。そのために診断書を作成します。
不安はいたずらに脳を疲弊させます。
脳は疲弊するとうつ状態となります。
うつ状態となると動けなくなってしまいます。
自宅療養を勧めるとともに服薬を勧めることもあります。
不安を軽減し脳の疲労を解消しうつ状態を改善する薬剤を用いることが多いです。
自宅療養中は病気で休んでいるからと言って周囲へ迷惑をかけていることを気に病みながら療養していると回復が長引いてしまうことが多いため、
なかなか難しいことではありますが、楽しく過ごすようにと必ず指導します。
日常が充実していると回復が早まります。
勿論、そうなってしまわないために、の段でもお話ししましたように、
生活を整えることも非常に大切です。
自宅療養で休んでいればよいと考えて夜更かし朝寝坊はいけません。
脳の調子が良くならないばかりか崩れてしまいます。
毎日起床と就寝の時間は一定を維持するようにとも
毎日時間を決めて体を動かすようにとも指導します。
復職に当たっては復職プログラムを利用する事が出来れば利用するよう勧めます。
混合性不安抑うつ反応・障害は職場環境に対する不適応が原因で生ずることが多いため、
復職に当たっては環境調整を職場に要請するよう指示します。
不適応が生じた元の職場で同様の仕事に携わると二次的併存症が再発します。
以上非常に簡単ではありますが、二次的併存症について、診断閾値未満(いわゆるグレーゾーン)についてご説明させて頂くとともに、診断閾値未満に多い二次的併存症としての混合性不安抑うつ反応・障害とその対策についてお話しさせて頂きました。
できるだけわかりやすくを心掛けましたがお話の内容の都合で用語が難しかったり説明不足だったりの所も多々あるものと存じますが、当職が及ばぬ部分は昨今ネットも検索やChatGPTなどといったAIが進歩しておりますので、個別にお調べいただけると宜しいかと存じます。皆様の興味を掻き立てることに寄与するなど、少しでもお役に立てれば幸いです。
練馬区民の皆様のこころの健康が増進する事を祈念して已みません。
誰にでも起こりえる産後うつ~産後のサポートが大切です~

ぱお助産院
院長 佐々木 美幸 様
「産後うつ」について知ろう
出産後、多くの女性が経験する一時的な気分の落ち込みを「マタニティブルー」といいます。出産によるホルモンバランスの急激な変化や疲労などが原因とされていますが、数日から2週間程度で改善するのが一般的です。「産後うつ」は産後2~3週間後から発症し数カ月間(1年以内が多い)続き、強い抑うつや不眠、食欲低下、興味・喜びの消失、希死念慮など、日常生活への支障も出てきます。原因としては、ホルモンバランスの変化、睡眠不足や育児疲労、育児のプレッシャーや環境の変化、夫や家族との関係性などがあげられます。
一般社団法人「いのち支える自殺対策推進センター」は、2025年7月に2022~2024年の3年間で妊産婦(妊娠中および産後1年以内)の自殺が162人に上ることを明らかにしました。そのうち産後3か月から1年の間の自殺が91人(56%)を占めています。同センターも、「妊産婦らは悩みを抱え込まずに相談してほしい」としています。
産後のサポートの大切さ
1.産後ケア事業について
産後ケア事業とは、母子保健法において「産後ケアを必要とする出産後1年を経過しない女子および乳児に対して、心身のケアや育児のサポート等(産後ケア)を行い、産後も安心して育児ができる支援体制を確保するもの」と定められています。練馬区は2016年度から産後ケア事業を開始し、現在までに事業者数や利用回数の増加、利用者負担額の減額、申請手続きの簡略化などの見直しを行い、拡充を進めてきています。「母子ショートステイ(宿泊)」「母子デイケア(日帰り)」「産後ケア訪問」3種類のサービスが利用可能です。
2023年からは国の「こども未来戦略」のなかで、産後ケア事業はすべての妊産婦を対象とした誰でも利用できるユニバーサルなサービスに位置付けられました。以前は練馬区も、産後ケア事業の対象条件として「育児不安が強い方、産後にご家族などから支援を受けられない方」が含まれていましたが、現在はその条件が削除されています。
私は2018年に産後ケアに対応できる助産所を区内に開設し、産後の母子と家族を中心に関わってきました。妊娠中からお腹に「いのち」を抱え、自分の「いのち」をかけて出産し、産後は身体の回復が不十分な段階で育児がスタートしていきます。私たち助産師は、ここに寄り添う職種なので、どんなに大変な経過であるか理解できます。産後ケアでは、温かい食事をゆっくりと食べ、授乳の合間にしっかり眠り、お風呂でリラックスし、助産師にいつでも相談できる環境で過ごし、心も体も元気を取り戻して帰っていきます。赤ちゃんだけでなく母親も大切にされて欲しいと思います。
2.産後は、だれもがサポートを必要とする時期
産後ケアの利用者さんの中には「私のような状況ではなく、もっと大変な人が利用するサービスだと思っていました」や、「母親は苦しいのが当たり前、家族のために頑張らなくてはいけないと、思い込んでいた」などと、話してくれる方がいます。新しい家族が増え、母親・父親役割への適応、家族関係の調整も必要な時期です。今までは無理してでも自分が頑張れば、家事も仕事も進んでいたかもしれません。しかし、育児については、家族だけでなく様々なサポートも活用し、皆で「分担」していくことが大切だと感じています。「疲れたな」「辛いな」「自信が持てない」などの気持ちの変化を伝えることができるし、周囲も気づいてあげることができると思います。
練馬区では、産後ケア事業だけでなく、さまざまな育児サポートを整えてくれています。妊娠中から情報収集しておけると安心ですが、産後の困った時からの情報収集・SOSでも大丈夫です。区の子育て支援の窓口に相談してみてください。
「生きづらさを抱えた方のこころの健康」 -訪問(アウトリーチ)という行為を通じて-
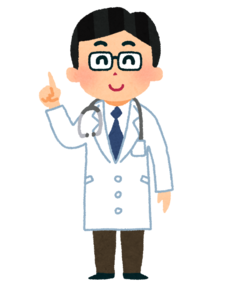
医療法人財団厚生協会 大泉病院
診療部長 木ざき 英介 先生
(環境依存文字のため、一部仮名書きとしています。)
【「生きづらさ」を感じながら生活すること】
今回、このテーマをいただき、自分なりにこの「生きづらさ」という言葉について考えてみました。
「生きづらさ」とは一つにくくりきれない、実に様々な意味が込められた言葉です。きっと学術的には様々な定義や説明もできるのでしょうが、多くの人が日々の生活のなかでも何気なく、ふと口にする言葉でもあります。思わず口から出る、その瞬間の私たちのこころのさしせまった状態や体験そのものもこの言葉には含まれるのだろうと思いました。
経済的問題や、自分・家族の健康問題を抱えたとき、親子・友人・職場での対人関係になやむとき、学業、進路、就職、仕事、介護など将来の不安をかかえたとき…このようなときに私たちは「生きづらさ」を感じる、といえるでしょうか。私は「生きづらさ」は様々な問題や状況に「いきづまること」から生まれるのではないかと思います。いうなれば“生きづまること”ということでしょうか。それは実に“息づまる”感覚であったり、こころも体も押しつぶされるような、閉じ込められたような体験をともなうものです。この状況におかれたとき、私たちはどのようにしてここから脱しようとするのでしょうか。
なんとか自らの力で解決していかれる方もいらっしゃるでしょうし、他の人の助けを借りて解決していかれる方もいらっしゃるかもしれません。問題は必ずしも解決できるとは限りません。「時薬(ときぐすり)」として時間が問題を解決してくれるまで待つこともあるでしょう。
そのようなとき、時に私たちはひきこもります。これは家の中にこもる、自分の部屋にこもる、という目に見えるかたちだけではなく、一見、通常の社会生活を送っているようでも、他の人との気持ちの交流を避け、自らのこころに没頭することも含みます。
ひきこもることは必ずしも悪いことではありません。そのようにして身をひそめ、こころが落ち着くのを待つことは理にかなっているといえますし、有効な対処方法の一つといってよいのではないかと思います。恐ろしい、息づまる外の世界から離れ、一休みし、思い、考え、そしてまた思い、考え、自らのこころを整理し、こころ穏やかな状態を作ろうとする。
しかしここで大事なことは、私たちのこころの世界が常に安心、安全なものばかりで満ちているわけではないということなのです。
【こころのなかの「物語」が生む孤立について】
私たちはこころのなかに自分固有の「物語」をもっています。
それは「自分はきっと~となるだろう」、「自分は~であるべきである」、「他人は~というものだ」、「世界は~というものだ」などというものです。この「物語」を精神(心理)療法の分野では幻想・空想と呼んだり、認知と呼んだりします。これは私たちの人生でつちかわれてきた決まりごと、ものごとの見方、その人の信念のようなものです。
そして私たちはこうした「物語」を目の前の現実と照らし合わせながら、時に無意識に重ねながら生きています。この「物語」は私たちが生きていく上での道しるべになります。「物語」は目の前の現実に改編され、ここから新しい「物語」が生まれることもあります。ただ私たちが生きていく上でこの「物語」とつきあっていくことは避けられません。この「物語」は私たちの助けとなることもある一方で、しかし時にそれは決めつけ、思い込みなどというかたちで、私たちの目を曇らせ、制約することもあります。
先ほど私は、私たちのこころは必ずしも安心、安全なものばかりではないと書きました。お気づきのように私たちのこの「物語」は楽しいものばかりではないのです。「物語」がその人を縛り、圧力をかけ、結果としてその人が傷つき、苦しむこともしばしばです。そして過酷な人生を歩んでこられた人にとっての「物語」が、悲しい、やるせないものであることもしばしばあります。
ひきこもる、ということは自分のこころと外の世界のあいだの壁を高くすることです。私たちにとって有害な現実と離れ、安心できる状態を作ることです。ただここでも私たちはこの「物語」からは離れることはできません。物語は私たちを制約し続けます。
私たちはひきこもらずとも日頃からこの壁を持っています。そして時に壁を低くしたり、目の前の現実に開きながらこの「物語」に従い、あるいは「物語」そのものを改編しながらこころのバランスを保っているのです。
しかし、ひきこもることを続けることは、「物語」と現実の接点がなくなっていくことを意味します。そこで思い悩み続けることは、「物語」がこころのなかで何度も繰り返され、現実による改編を受けないまま、やがては私たちの体験する世界そのものとなってしまう危険性を抱えています。つまり「物語」が、今風に言えば“事実(ファクト)”になるのです。当然過酷な「物語」も“事実(ファクト)”となりえます。身を守るためのひきこもること、は逆にその人を目の前の現実から引き離し、「物語」に閉じこめ、追い詰めるもの、となってしまうのです。ここに「孤立」が生まれるのではないか、と私は考えています。
【アウトリーチを通じてできること】
私は、現在、精神科の病院に勤務していますが、主にアウトリーチという方法で診療を行っています。アウトリーチとは、「援助が必要であるにもかかわらず、自発的に申し出をしない人々に対して、公共機関などが積極的に働きかけて支援の実現を目指すこと。医療機関が、在宅の患者や要介護者を訪問して社会生活を支援する活動など」(大辞林)を意味します。
なにがしかの事情で自宅から出られない方を対象に、私は訪問し、支援を行っています。
この方法はこの「ひきこもる」状態にある方への支援といえるでしょう。先ほどまでのお話からすれば、現実から閉じられたその方のこころの世界にその外側からかかわっていく試みであるといえるでしょう。そして、その方の「物語」と現実が接点を取り戻し、こころのバランスを取り戻していただくようになるお手伝いができればと考えています。
ただ先に書いたように、「ひきこもること」はその方を守ることでもあります。
アウトリーチという行為が、私たちが壁を越え、その方のこころにかかわるという行為が、その方にとって今どのような意味を持つのか、安らぎを妨げるものなのか、「孤立」に苦しんでいるかもしれないその方のなにがしかの助けとなるものなのか、日々考えながら、チームメンバーと共に診療にあたっています。
自律神経を整えて健康管理を

産業医 竹村 雅代 先生
新型コロナ感染症や度重なる震災など、環境変化は私たちの大きなストレスになります。また、私たちは、普段の仕事や家庭生活でも大小様々なストレスにさらされています。このようなストレスからどのように自分の健康を守っていけばよいでしょうか。
健康な生活を維持していくためには、規則正しい生活、十分な睡眠、バランスのよい食事、運動、気分転換を取り入れるなどがよいでしょう。これらを心がけると自律神経が整い健康な生活を送ることができます。
今回は、自律神経の仕組をご説明し、特に副交感神経をうまく利用し、自律神経のバランスを整える方法をご紹介します。
【自律神経とは】
人間の身体を動かしたり、感覚をつかさどっているのは、「運動神経」と「自律神経」の2つがあります。運動神経は脳や脊髄からの指令を筋肉に伝え動かすための神経で、自分の意思で動かすことができます。これに対して自律神経は、自分の意思で動かすことはできません。具体的には胃、腸、心臓、腎臓など様々な臓器の動きや血圧、血流などをコントロールしています。私たちの意思に関係なく、起きているときも寝ている間も、様々な体の機能をコントロールしてくれているのです。
【交感神経と副交感神経】
自律神経には、「交感神経」と「副交感神経」の2種類があります。交感神経は体を緊張させる方向に働き、副交感神経は体をリラックスさせる方向に働きます。この2つの神経は真逆の機能を持ちながら、シーソーのように互いにバランスをとりつつ身体の機能を調整しています。ですから、非常に緊張しているときは交感神経が優位になり、とてもリラックスしているときは、副交感神経が優位になっています。この2種類の自律神経がうまくバランスが取れていると、様々な身体機能を良好に維持していくことができますが、逆にバランスが崩れると健康障害が出やすい状態になります。
【呼吸を使って副交感神経優位の状態を作る】
ストレス下では、私たちは緊張したり焦ったり頑張りすぎたりしがちで、体は緊張を強める交感神経優位の状態になるため、それを副交感神経優位にしてあげるとバランスが取れるわけです。ところが、自律神経は自分の意志でコントロールすることはできません。しかし、呼吸によってコントロールすることが可能になります。
副交感神経優位の状態にするには、「ゆっくりした呼吸」「深い呼吸」が有効です。普段から「ゆっくりした呼吸」「深い呼吸」を心がけましょう。
また、「ゆっくりした呼吸」になるために有効な方法があります。それは「ゆっくり行動する」ということです。行動がゆっくりになると、自然に深い呼吸ができたり、呼吸を意識することができます。
簡単な行動で大丈夫です。例えば、パソコンのキーボードを打つスピードをゆっくりにする、字をゆっくり書いてみる、お皿をゆっくり洗う、話すスピードをゆっくりするなど何でも有効です。
私は忙しいとき、トイレの時間も勿体なく、廊下を突進して歩いていましたが、最近は忙しい時こそ、ゆっくり歩いてトイレに行くことを心がけています。そうすると不思議なことに気持ちが落ち着き、肩の力が抜け、リラックスした気分になれます。
とても簡単な方法ですので、ぜひ、ゆっくり呼吸、ゆっくり行動を日々の生活に取り入れ、自律神経のバランスを整え、健康な生活を送っていただきたいと思います。
大事なもの(こころ)は目に見えない
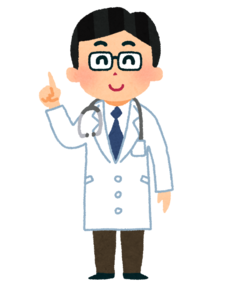
医療法人社団康優会 染谷メンタルクリニック
院長 染谷 康宏 先生
こんにちは。染谷メンタルクリニックの染谷です。
今日は「こころ」という形ないものに精神科医がどうやってアプローチしていくのか、その一端でもお伝えできたらと思います。
当たり前ですが、「こころ」は目に見えません。
いま頭に浮かんでいる考えが本当の気持ちなのかどうか…怪しいことも多いのです。
例えば、好きな相手がいたとしましょう。
好きすぎると近づけない‥‥好きなんてとてもじゃないけどなかなか言えません。
もっと好きになると‥‥逆につい冷たくしてしまう。
もっともっと好きになると‥‥相手の些細な欠点を見つけて「ああやっぱりひどい人だったんだ」とつい離れたくなってしまう。
あれ、本当は好きで近づきたかったはずなのに。
なんでなんだろう?なんでこうなるんだろう?自分の行動と本当の気持ちが分からない。そんな自分が嫌になる。何度か同じような後悔が続いた時…。
そんな時に一緒に考えるのは我々精神科医の大事な役目です。
好きになればなるほど、近づいて否定されるのが怖かった。嫌いだと言われ自分が傷つくことが怖かった。自分を守りたくて、その自分の弱さにも気が付きたくなくて、相手の小さな欠点を故意に大きくして自分が離れようとしたのだ。相手ではなくて自分の問題だったと。
話すうち、自分を見つめていくうちに、このような「こころ」の動きに気が付くかもしれません。
このような思考と感情の「解離」は決して少なくありません。
親、兄弟、姉妹、などの肉親者と自分との関係。学校や会社などの組織と自分との関係。社会の価値観と自分との関係。
親が勧める社会的地位の高いもしくは給料の多い仕事に就いたが、深い喜びが感じられない。逆もあり得ます。支配的だったと思う親に逆らって家を飛び出し、家業も捨てた。
しかし、なぜか家業が気になって仕方がない。親が亡くなったのちこんなにも親を愛していたのかと気が付く。
「解離」は当然ながら多くの場合、不満足や欲求不満をもたらしますから深い自己肯定を阻害します。分かりやすくいえば、いつもイライラしがちで満たされない、妬み嫉みが強くなり、他人の幸せが憎くなることが多いのです。
本当の深い願望に沿うことは本当の自分を生きることにつながりますが、それは時として親を含めた他者の意向と対立することもあるわけです。愛されなくなるかもしれません。否定されるかもしれません。怖いことかもしれません。
何が君の幸せ、何をして喜ぶ、分からないまま終わる、そんなのは嫌だ。
アンパンマンには遠く及びませんが、あなたの側であなたを勇気づけたい。
精神科はそういう出会いをする場所だと私は思っています。
我々の有限な人生。
不自由を感じたら、自分を好きになれないと感じたら、偏見を持たず「ひとかけらの勇気」を持って精神科を訪ねてみてください。
私の深い願いです。
オーバードーズとこころの健康

医療法人社団アパリ アパリクリニック 理事
医療法人社団ヒプノシス 雷門メンタルクリニック 医師
精神科専門医・指導医 梅野 充 先生
オーバードーズとは?
オーバードーズOverdose(以下、「OD」オーディー)とは、薬剤を規定より大量に服用することをさします。近年、かぜ薬などを症状を抑えるためではなく、感覚を変化させたり気分を楽にしたりする目的で大量に服用することをさすようになっています。このコラムでは、精神科臨床医の立場からODとこころの健康についてお伝えしたいと思います。
抗不安薬や睡眠薬のOD
かねてより、精神科医師が処方する不安を軽減するための薬(抗不安薬)や睡眠薬を多めに服用する場合がありました。患者さんご自身は「睡眠薬を連用しているうちに次第に効果が薄れてきて多く服用するようになった」、「不安になる前に服用しているうちについ大量に飲むようになってしまった」などと説明されます。なかには「暇だから飲んでみた」などというかたもあります。
「1日に2錠まで」の規定のある薬を、何十錠の飲むようになってしまったという人もあります。しだいに処方薬が足りなくなってあちこちの医療機関をはしごして規定量以上に入手しようとする人や、医師を脅して多く薬を処方してもらおうとするような人もあったと聞いたことがあります。近年は薬剤の管理が厳しくなり、上記のような処方薬のODはできなくなってきているものと考えられます。
ODの薬理学
そもそもこうした薬剤は長期的に服用を続けることが前提で安全に作られています。規定量は余裕をもって安全な量に定められているものです。かつて大作家が睡眠薬をのんで自殺を図ったといった事件がありましたが、現行の薬剤ではODしたとしても死にいたるようなことはあまりありません。そこでそれ以上飲んだとしても人によってはにわかに副作用がでず、次第に用量が増えてしまうことが起こるのです。
こうした薬剤には「耐性」という性質があって、長年月、連用しているうちに効果が減弱していきます。こうした際には医師は可能な量までは増やしてそれ以上効果がでないようであれば別の薬剤に交換して再び効果を得るように調整します。一般の患者さんがなんとか十分な効果を得ようとして多めに服用するようになってしまうのです。
ODと依存症
次第にいつも体内に薬剤の効果がないと不安になるようになり、これを「精神依存」と呼びます。あるいは耐性のために、以前と同様の効果を得るためには大量の薬剤が必要になり、さらにいつも一定の薬剤を連用していないと体調が悪くなる(離脱症状)ようになります。これを「身体依存」とよびます。
このように精神依存や身体依存が起きて薬物使用に関するコントロールができなくなり、みずから「減らしたい、やめたい」と思っているのにも関わらず、薬物摂取を続けてしまうようになります。この状態が「依存症」です。
薬物に対する依存だけでなく、大量飲酒を繰り返したり、ゲームやギャンブルをやめられなかったり、過食や浪費をやめられなかったり、など様々な行動についてコントロールができなくなることがありえます。これらは本来の本人の意志力や倫理観とは関係なく起きる行動です。
ODについても同様に、先ほどの「耐性」、「離脱症状」などのためにしだいに使用量が増加し、そのあげく大量に服用することが習慣化している依存症の一種であるとみることができます。
ODに至りやすい薬剤
ODに至りやすい薬剤としては、上記のように睡眠薬や抗不安薬が代表的ですが、近年は総合感冒薬、解熱鎮痛薬、鎮咳薬などが増えてきています。
睡眠薬や抗不安薬の多くは「ベンゾジアゼピン系」と呼ばれる薬剤で、脳内のベンゾジアゼピン受容体に働きかけてGABA(ガンマアミノ酪酸)という物質の働きを刺激して抗不安作用や催眠・鎮静作用などをあらわし不安障害や心身症などの諸症状を改善するとされます。
ブロムワレニル尿素という成分が含まれる睡眠薬や鎮痛薬は鎮静作用があって眠気を催すとされます。さらにジフェンヒドラミンを含む睡眠改善薬やかゆみ止め薬もODされることがあります。
また感冒薬や、鎮咳薬のODについては、麻薬性鎮咳薬のジヒドロコデインリン酸やエフェドリンが関連しているものとされます。またデキストロメトルファンという咳止め成分が含まれる薬剤がNMDA受容体に作用して中枢効果をもたらすとされます。さらに、中枢神経を覚せいさせ、他の成分の効果を高めるカフェインが含まれている売薬もあり、これも依存を引き起こす原因である可能性があります。
ODにいたる心理
ではODとはどのような心理的なメカニズムによって引き起こされるのでしょうか?私としては「覚せい度」を変えて気分を調節しようという、「自己治療」によるものととらえています。
われわれの意識の状態は「覚せい度」によって決まっています。覚せい度が低いと眠くなり、高いと冴え冴えとして冷静になり、高すぎると緊張が高まってイライラとしてきます。また気分が落ちるとうつ的でエネルギーが低下し虚無的になったり厭世的になったりし、気分が高まるとそう的で多幸的になってエネルギーが出てきます。
ODをこころみる若い人たちの中には、強い「生きづらさ」を抱えている人がいます。つまり気分が落ち込んで生きる意味が見いだせないような人や、家族や他人とのコミュニケーションに困難を感じて生きることに苦しむ人たちです。
気分が下がってうつ的になると、空疎さや虚無感を感じてなにもかもに価値がないように感じて生きる意味をみいだせなくなります。そこで覚せい度(テンション)をあげるためにお酒を飲んだり、ゲームや「推し活」に熱中したりします。テンションがあげるような作用を示す薬剤をODするようになります。
逆に気分が上がってそう的で空回りするようになると、物ごとの細部に注意が集中されてさまざまなことが気になって、つらくなり、コミュニケーションにも困難をきたすので、覚せい度を下げてリラックスすることが必要で、そのためにODが必要になる場合もあるでしょう。
このように気分やテンションの調節のための「自己治療」としてODをしているものと考えることができます。リストカットやあるいはバイクなどでの暴走行為なども同様のメカニズムによるものかもしれません。いわば「自己破壊衝動」の表れということができ、または逆に「なんとか生き抜くためのせめてもの悪戦苦闘」と言えるかもしれません。
ODからぬけだす
ではお子さんたちがODから抜け出すために、家族や大人世代の我々には何ができるでしょうか?精神科医療としてなにか特効薬的な治療や方法があるということはできないのが現状です。
臨床経験では、感冒薬や睡眠薬などをODしている人にとってそれらが必要な状態や段階を脱するように、治療者や周りの人たちが働きかけようとすることは難しいことが多いように思われます。ただ、特に若い人たちにはそこから抜け出す、タイミングというか、機が熟する時がきて、自然とそういう状態を脱することがある、という気がしています。
たとえば学校になじめないものを感じていて、なんとか登校したい、と思いながらできない、親に心配をかけたくない、という思いから学校にいけない自分を責めてしまう、という思いがある人があるとします。ひとこと親から「学校に行かなくてもいい、あなたがおだやかに暮らせればそれでいい」と言ってもらうだけで本人は肩のちからが抜け、緊張や不安を落ち着かせるためのODが必要でなくなるような場合があるかもしれません。
どこかでODのような方法による気分の変化が必要でなくなる時がくる、そこまでなんとかODしている時期をやりすごしてもらう、家族が本人のことを案じて、でも将来の幸せを信じることが次のステップへのきっかけになるように思います。
ODしている人に家族や知人ができること
ではODする人にご家族や周りの人は何ができるでしょうか?積極的にODさせないために何かする、というよりもODしている状態を、長い目で見てそこを通り過ぎるのを待つ、というような対応になると思われます。
本人や自分自身を含むだれかに責任を帰して責めたりすることではなかなか解決しないのが依存の問題です。「泣き落とし」や「交換条件」によって行動を変えることも依存症においては困難な場合が多いです。
長期間かかることも多い問題ですが、自治体としても相談窓口が用意されています。区での家族相談や、東京都の精神保健福祉センターでの依存症家族教室なども利用可能ですので、まずはご家族だけで相談をしてみることをお勧めします。
まとめ
現在、話題になることが多いODの概要とその心理、回復にむけてのヒントを少しお伝えしました。ODになやまれるご本人やご家族には苦しみが強い場合もあるかもしれません。相談にいらっしゃることで、少しでも回復に向けてのお手伝いができればとの思いでおまちしております。希望をもって少しでも前に進んでいきましょう。
依存症治療の最前線にて
医療法人社団ヒプノシス 雷門メンタルクリニック
院長 伊波 真理雄 先生
【はじめに】
精神科で研修医をしていた平成3年から依存症治療に興味を持ち、翌年にはアメリカでの研修に参加しました。そこでたくさんの回復者と出会い、彼らのボランティア活動に刺激を受けました。その後わたしは上京を決断し、依存症回復施設のボランティアスタッフとの協働を30年続けてきました。いまだに新たな疑問や課題にとまどいながらですが、精神科医師として充実した毎日をおくっています。
【依存症とのたたかいと敗北】
初めての依存症臨床経験は沖縄でのアルコール専門病棟勤務でした。
あの頃は治療プログラムを終えて退院した後、3年以上断酒できた人は利用者の1割もおらず、徒労感や無力感にとらわれていました。
また同僚の医師やナースたちからも「依存症とは関わりたくない」と言われ、理解や協力が得られないまま、怒りや孤独感も感じていました。
だけど今ふり返れば、あの頃はわたし自身も「依存症は治らない病気」とか、あるいは「がんばった人だけが立ち直る病気」と考えていたように思います。
【新しいプログラムとの出会いと変化】
アメリカの依存症回復施設で学んだことは、回復を見守る側のまなざしがいかに大きな影響を与えるかでした。わたしは日頃「いかに飲ませないか」と夢中になって、自分の治療成績ばかりにとらわれていました(きっとその頃のわたしはコワイ目をしていただろうと思います)。
おだやかなまなざしの回復経験者たちと出会ってからの30年で、ずいぶんとわたしの依存症へのむき合い方は変わりました。たとえ今、依存症の渦中にあり、シラフになるのが怖くて、少しでも自分の状態を良く見せようと焦っている人たちも、介入のタイミングさえ間違えなければ、ありのままの自身を受け容れ、解放感に満ちた日々を取り戻せると信じるようになりました。
【今のクリニックでの依存症支援】
平成12年に浅草で開業してからも、依存症の回復施設との連携は続いています。
せっかくリハビリにつながっても、医療機関で多種類の向精神薬が処方されていると、ボランティアスタッフの判断では減薬できないこともあり、私のクリニックでは「ラクで、クリーンで、自由な生活」に向けて、ほとんどの利用者が向精神薬を中止できるよう見守っています。
もう一つは合併症の存在です。成人の発達障害などの鑑別依頼も増えてきました。
知能検査や発達経過の聴き取りで、アルコールなどの物質乱用に陥る前からの「生きづらさ」を把握することや、6ヶ月以上シラフで経過観察を行ない「重複障害」を確認できれば、個別の支援プログラムも提案しています。
【おわりに】
平成22年6月に国際的な諮問機関から「物質使用には懲罰ではなく治療へ」と宣言されましたが、日本のメディアではまったくと言っていいほど取り上げられませんでした。
海外の物質乱用先進国に比べれば、わが国では厳罰による取り締まりによって、違法薬物にはある程度の成果をあげているのかもしれません。しかし依存症から再チャレンジしようとしている人への理解や支援は、私たちのアピール不足もあり、「残念なレベル」と表現せざるを得ません。
思いがけない形で依存症とかかわり、医師としてたくさんの得難い経験をさせてもらいました。これからもその感謝と喜びを伝えつつ、回復経験者によるボランティア活動が、さらに広がっていくことを願ってやみません。
ギャンブル依存症の家族とこころの健康

公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会
代表 田中 紀子 様
ギャンブル依存症の家族に生まれ育って
私は父がギャンブル依存症で会社の金を横領しました。母はこれをきっかけに父と離婚し実家に戻りましたが、実家の祖父もパチンコ依存症でした。
そのため我が家は常に貧しく、必要な学用品もなかなか買ってもらえないような状況でした。祖父母からは「お前がいると金がかかる」「孫なんか飼っておくもんじゃない」こんなことを言われ、母は「世間の奴らはうちを笑っている。いい学校、いい会社に入って見返せ」と私に言い聞かせながら育てました。
私はそんな日々が辛くて「早くこの家を出ていきたい」「親のようには絶対にならない」と思って生きてきました。
それなのに、なぜかギャンブル依存症の夫と結婚してしまいました。
夫は、とても優しい人で声を荒らげたことなどありません。仕事もできて収入も高く、高学歴でした。
ギャンブルが好きなことも重々承知していましたが、怠け者で働くことが嫌いだった祖父とは違い、仕事もしっかりやるし、みんなに信頼もされているし、男はみんな少しくらいギャンブルをやるもんだろう。そんな風に考えていました。
そして一緒にギャンブルをやっているうちに、自分もギャンブル依存症になってしまったのです。
けれどもその頃の私たちは、まさか自分たちが依存症だなんて、全く思ってもみなかったのです。
度重なる借金と肩代わり
二人でギャンブルにはまると、当然借金だらけになりました。とても気が合い、お金のこと以外では喧嘩などしたことがありませんでしたが、段々経済的に追い詰められていきました。結婚したらきっと真面目になるだろうと思い、結婚をして転職もしました。そして私たちはその後も実験を続けました。「子供ができたら」「家を買ってローンができたら」「子供が二人になったら」「もっと大きな家に買い替えてローンを増やしたら」私たちはきっとギャンブルをやめて真面目になれるだろう。こんなことを考え繰り返していました。
でも今振り返ってみると、私たちは不真面目だからギャンブルをやっていたのではなく、子育てをしながら、共稼ぎで住宅ローンや教育費、そしてギャンブルの借金を返済できるだけの収入を得られるほど、サラリーマンとして稼ぐという十分真面目な生活をしていたのです。それなのに、「自分たちは不真面目だ」「もっと頑張らなくちゃ生活が安定しない」と自分たちを責めていました。
「ギャンブル依存症という病気です」
年子で生まれた子供が2歳と3歳になった時です。また夫の借金が280万円ほど出てきました。私は、自分のことはさておき、激怒し怒鳴りつけました。
「あんたは病気よ!」「知ってる?馬鹿は死ななきゃ治らないって言うのよ」すると夫は突然泣き出し「俺、本当に病気なんだ。自分じゃやめられない。助けてくれ」と言ったのです。これが我が家のターニングポイントになりました。
この夫の一言から、私たちはギャンブル依存症の専門医に繋がることができました。先生から、「ギャンブル依存症という病気です」と言われた時には、訳が分かりませんでしたが、解決策の光が見えた気がしました。
そしてこの主治医から「奥さん、あなたは共依存状態です。ご主人の借金を肩代わりしたり、自分のことのように責任をしりぬぐいしています」「二人ともギャンブル依存症の自助グループに行きなさい」と言われました。
こうして私たち夫婦は、夫はギャンブル依存症の当事者、私はギャンブル依存症の家族の自助グループに行くことになりました。そして夫婦で回復することができたのです。
ギャンブル依存症の家族になったら
もし、あなたの家族がギャンブルによる借金を繰り返していたなら、あなたはギャンブル依存症の家族として、すぐに対応を学びましょう。
今は、全国に「ギャンブル依存症家族の会」という団体があるので、そこに繋がってみてください。みなさんと同じ経験をしたご家族が、力強いサポートをしてくれます。
ギャンブル依存症者には以下のことをやりがちですが、これは逆効果です。
1)借金の肩代わりをする
2)説教をしたり、念書を書かせたり、もうやらないと約束させる
3)金銭管理や行動管理をする
おそらく相談に来られるまで、ギャンブル依存症のご家族はこの間違った手助けを繰り返してこられたと思います。ですからそれをやめろと言われても、やめるのがとても怖いはずです。けれども別名「否認の病」とも言われる、自分でなかなか認められないギャンブル依存症という病気から回復するためには、自分でやったことの結末を苦しみながら体感し「こんな生活は嫌だ!もう抜け出そう」と思えることが大切なのです。
家族が、借金や責任を肩代わりしていたのでは、いつまでたっても抜け出そうと思えません。
お金を出さなくなったら、ギャンブル依存症者は「もう死ぬしかない」「闇金に借りる」「犯罪をやってやる」などと脅したり、泣き落としにかかるかもしれません。
家族は心がグラグラします。見ているのが辛いし、心配だし、可哀そうにもなって、つい払いたくもなるでしょう。
そこをぐっとこらえて「ギャンブル依存症の支援団体に相談しなさい。家族はもう何もできない」と突っぱねるのです。その折れそうな心を支え、その場に適した言葉をレクチャーし、当事者の動きに合わせて臨機応変に対応してくれる、それが家族会です。
家族会の協力で、当事者を自助グループや、病院、回復施設につなげられた人は数多くいます。家族は一人で抱え込むのをやめ、自分の応援団を作りましょう。
病気だから回復できる
私たち夫婦は「ギャンブル依存症は病気」と理解できた日から回復することができたのです。「自分は意志が弱い」「不真面目な人間」「だらしがない奴」と性格の問題だととらえていた時は、どれだけ努力しても全く回復できませんでした。
ところが病気だとわかり、それを受け入れたら、「自助グループ」という回復方法が見つかったのです。
ご家族も「病気なんかじゃない」と否認せず、「病気なら回復できる」と捉え、ぜひあなたの応援団に繋がってきてください。きっと光が見えるはずです。
お問い合わせ
健康部 保健予防課 精神支援担当係
組織詳細へ
電話:03-5984-4764
ファクス:03-3993-6553
この担当課にメールを送る
このページを見ている人はこんなページも見ています
法人番号:3000020131202
練馬区 法人番号:3000020131202